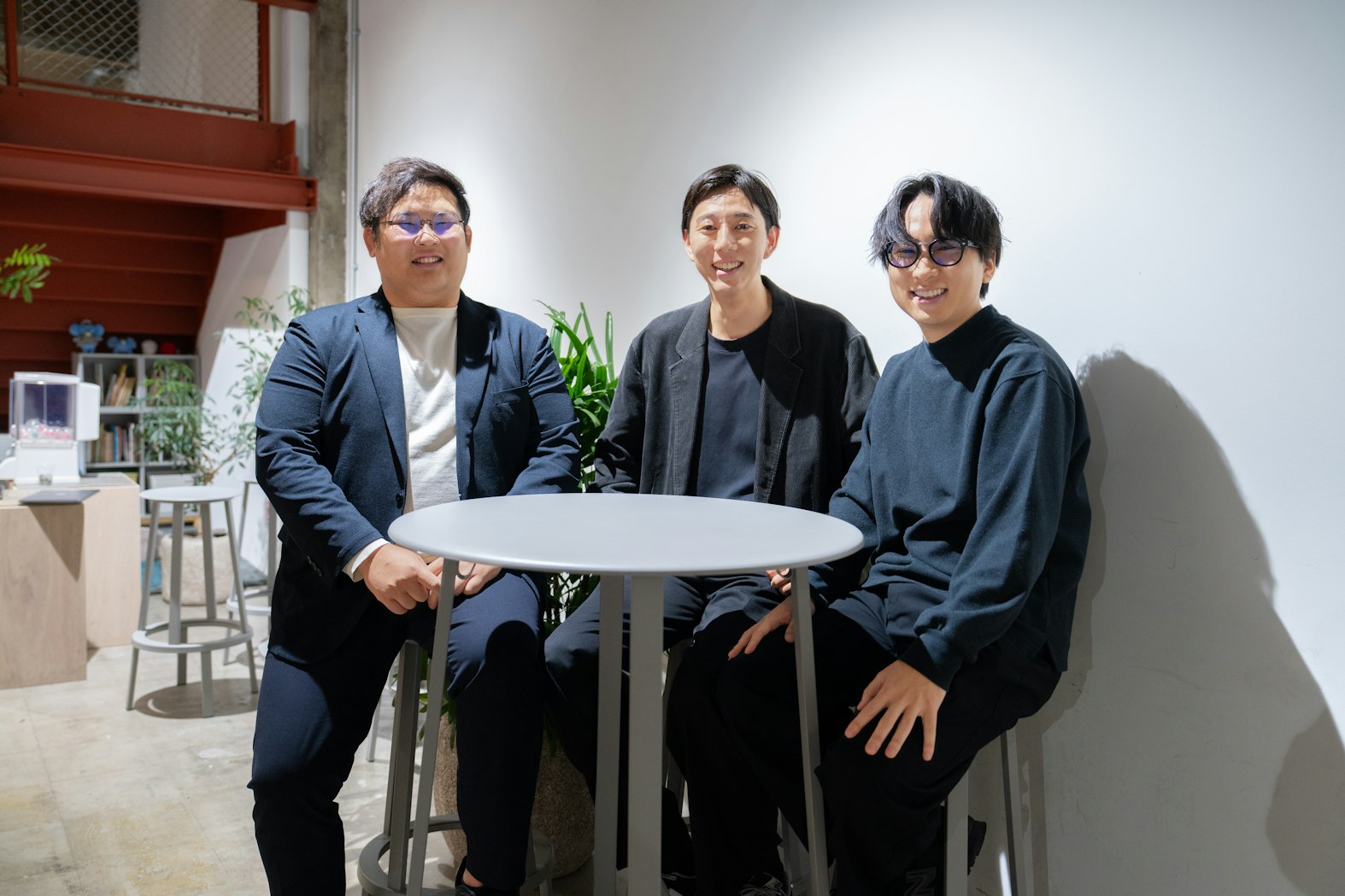「質の高い活動量」をどう生み出すか
田本 圭史朗(以下「田本」):
プロジェクトを立ち上げた背景は大きく2つあります。ひとつは、やはり生成AIの台頭です。もうひとつは、インサイドセールス(以下「IS」)の生産性ってもっと上げられるよね、という課題意識がSpeeda事業全体としてあったことです。
生成AIを活用して生産性を上げていく未来が見える中で、これをどう推進していくか。私と佐藤とで、共通の課題感を持っていました。
田本:
実務ベースで言うと、たとえばメールの作成業務や商談メモの作成、自身のコールを振り返るためのフィードバック作業などですね。こうした業務を効率化できないかなと。
ただ、我々がトップダウンでガチガチのオペレーションを決めてしまうのは、AIが出てきたばかりのこの段階ではナンセンスだと思っていました。そうではなく、まずは現場のメンバーが生成AIを触って、みんなが自由に活用できる。そんな土壌をいかにつくれるか? という点を主軸にプロジェクトを始めました。
田本:
大きな課題として3点ありました。まず1点目は、「質の高い活動量を担保していく」ことです。当時、残業時間とトレードオフでパフォーマンスを出しているメンバーもいました。いわゆる事務作業の時間を生成AIでいかに短縮し、お客様としっかり対話する時間を増やせるか。これが大きな課題でした。
2点目は、AIを「活用できるメンバー」と「活用できていないメンバー」の差がすでに出ていたことです。一部のメンバーは生成AIをどんどん活用して業務をブラッシュアップしていく一方で、事前準備やターゲティングに疲弊してしまっているメンバーもいた。この差を平準化したいという想いがありました。
そして3点目が、"再現性のある"生産性の向上です。単純に「活動量を上げる」「メール数を増やす」という目標を掲げるだけでは、3ヵ月は走れるかもしれないけれど再現性と持続性がない。結果的にメンバーが疲弊して辞めてしまう、といった最悪のケースも考えられます。そうではなく、コールやメールといったISとしての本質的な活動に時間をしっかり割くために、事前準備などの時間をいかに少なくするか。この点を強くメッセージとしていました。

佐藤 磨央(以下「佐藤」):
インサイドセールスとしての我々の最重要ミッションは、「顧客接点の最大化」です。つまり、お客様と向き合い、一次情報を取りに行くことが最も重要なんです。
その点で、生成AIはあくまで「人が主役になるための手段」だと思っています。人でしかできない泥臭い活動──たとえばお客様と向き合ったり、接点を持ったりする活動にどれだけ時間を投資できるか。そのために、今の活動の質を高めて生産性を上げていく必要がありました。
佐藤:
はい。そもそも僕らの組織は「強度」がすごく高いんです。
佐藤:
コール数やメールの量、お客様と会う頻度といった活動量や、実行する施策に対してのコミットメントです。その強度をさらに上げたり、スケールさせていったりするためには、生産性の向上が不可欠でした。強度だけが高い人と、生成AIの活用だけがうまい人、という状態だと、成果は途中で止まってしまう。両方を掛け合わせ、組織全体でスケールさせるための手段として、今回のレッドロックプロジェクトが生まれました。
次世代リーダーを育てる仕掛け
田本:
評価軸は2つです。まず、定量の成果。生産性が上がったかどうかを証明する部分で、これが全体の7割を占めます。そして残りの3割が定性面。具体的には、Notionにナレッジを蓄積していくんですが、ナレッジを活用したらSlackでスタンプを押すルールにして、その数で評価しました。定量に主軸を置きつつも、組織全体のモメンタムを作るために定性面も評価対象にした形です。
田本:
はい。そして、実はもうひとつ、裏の目的がありました。それは、次世代のリーダー人材の発掘です。
このプロジェクトでは、既存のチームとは別に、新たに7チームほど組成しました。そして各チームに「キャプテン」を任命し、ピープルマネジメントはしませんが、ナレッジを循環させる役割を担ってもらいました。
プロジェクトの立ち上げこそ我々がやりましたが、その後の運用やモメンタム形成は、すべてキャプテンたちに任せました。僕らはほぼノータッチです。すると、その中でリーダーシップを発揮して、全体のモメンタムをつくってくれるメンバーが現れたりするんですよ。
田本:
長島さん(長島 翔/IS部門所属)のチームがまさにそうですね。
佐藤:
あの動きは素晴らしかったですね。僕らはナレッジを浸透させ、循環させることを大切にしていますが、どうしても「ナレッジをいかにして循環させるか」という課題がありました。そこにメンバー自身が課題意識を持ってくれたんです。
「出したナレッジを、メンバーが実際に使える状態にしなきゃいけないよね」と。その解決策として、長島さんが「組織としてナレッジをすぐに呼び出せるチャットボットのような仕組みをつくりたい」と発信してくれたんです。
その声を受けて、キャプテンだった吉田さん(吉田 竜也/IS部門で長島と同じチームに所属)も「じゃあ、それを実現するためにどうしようか」と、他の部署とも連携しながら実現に向けて動いてくれました。もともとあった課題に対して、現場で原体験を持ったメンバーやキャプテンが動き出し、結果として素晴らしい仕組みが生まれた。こういう機会をつくったことで、彼らが意志を持って進めていくことができたのは、プロジェクトの大きな成功だったと思います。

田本:
これはもう、AIではなく完全アナログですね(笑)。本当に1人ひとりバイネームで見て、特性が合いそうだったり、相互補完ができそうだったりするメンバー同士を組み合わせました。
佐藤:
たとえば、吉田さんと長島さんのチームは分かりやすい例です。2人ともAI活用や効率化がすごく得意。じゃあ、得意と得意を掛け合わせたらどれだけうまくいくのか、と。逆に西村くんたちのチームのように、気合と根性があるメンバーと、仕組み化が得意なメンバーを合わせたり。
田本:
そうです。戦略は考えられるけど実行力が弱い、という人がいれば、そこを補い合えるメンバーを組み合わせる、といった形ですね。
佐藤:
また、キャプテンに選んだのは、ネクストリーダーとして期待したい人です。役割や期待によって人は変わり、成長をします。今は役割がないだけで、自分でキャップをはめてしまっているメンバーにキャプテンという役割を与えて、チームを率いるチャレンジをしてもらう。それが、その人にとっての次の一歩につながるんじゃないか、と。
私もユーザベースのリーダーたちからたくさんのチャレンジをさせてもらった原体験があるからこそ、そういった観点で、キャプテンやメンバーの選定はかなり考え抜きましたね。そこはAIを使わずに(笑)。
田本:
ありました! 先ほど話に出た吉田さんと長島さんのチームですが、ここは優勝候補だと思っていたんです。でも実は、2人のマネジメントスタイルやアクションスタイルの違いから、最初に対立が起きてしまって。
佐藤:
僕が直接間に入ったのでよく覚えているんですが、2人とも思想は同じなんです。よく例えるんですが、「パソコンのOSは一緒だけど、アプリが違う」みたいな。事業成長へのコミットも、周りを巻き込む力も、AIを活用するスキルも同じ。
ただ、チームビルディングにおけるアプローチが違いました。吉田さんは、チームやメンバーのネガティブな感情を受け止めながら、吐き出させながらチームを前に向かせていくスタイル。一方で長島さんは、とにかくチームを前進させるために、ネガティブな発言をできる限りせず、ポジティブに捉えながらチームをつくるスタイル。タイプ。
2人ともチームを良くしたい、強くしたいという根幹の思想は同じだけど、アプローチの仕方が少し違うんですね。吉田さんがみんなを盛り上げようとして発した言葉を、長島さんはそう受け取れなかった。そこですれ違いが起きてしまったんです。
佐藤:
まずは、ちゃんと対話する場を設けました。ユーザベースには「対話」の文化があります。相手のことを想像はできるけど、あくまで主観。なので実際に話してみないと、なぜそう考えたのか、そうしたコミュニケーションを取ったのかはわからない。話してみると、お互いの考えが分かり、彼ら自身も「あ、だからそういう考え方・伝え方だったのか」と納得できた。
この経験を通じて、2人のコミュニケーションもすごく変わりましたし、そうした健全なコンフリクト(衝突)が我々の成長につながった良い例だと思います。
田本:
はい。特にNewJoiner(中途入社者)たちの動きは印象的でしたね。2025年7月に入社したばかりのメンバーがプロジェクトに参加したんですが、彼らは自分たちのオンボーディングで起きている課題を話し合い、自らキャッチアップのための資料を作成してくれたんです。
入社したばかりで、どうやって自分の力を試せばいいか分からない。そんな状況でも、「どんどん発信していこう」という文化がチームの中に醸成されていたことで、彼らの主体性が引き出されたのだと思います。
ナレッジを「自分ごと」にしたメンバーの変化
西村 幸大(以下「西村」):
率直に、面白そうな企画が始まるなと思いました。ただ、私は今回のプロジェクトを推進できるタイプでは全くなく、どちらかというと「気合と根性」で成果を出してきたタイプなんですよ……(苦笑)。
なので、今までの自分のやり方で、みんなにシェアできることってあるのかな? とか、お役に立てることってあるのかな……という不安はすごくありましたね。
西村:
そうですよね。なので、「自分から何かを提供できるか」という不安はありつつも、新しいやり方を取り入れることで自分を変えていけるチャンスなんだろうな、と。そういうマインドで捉えるようにしていました。

西村:
ありがとうございます! 一番の勝因は、ナレッジへの情報感度を高く持ち続け、実行したことだと思います。Notionをとにかく見ていました。
長島さんや吉田さんをはじめ、マーケティング・IS本部全体でプロジェクトを盛り上げていこうという空気をすごくつくってくれていたので、そこに出てくるナレッジを「自分だったらどう使えるか」と常に考えていました。
正直、このままのやり方を続けても、どこかで限界が来るだろうと感じていたんです。何かを変えないと、これ以上の成果は出せないな、と。そのため、このレッドロックプロジェクトを自分にとって価値あるものにしようと考えていました。本当に、ただそのマインドだけで乗り越えた感じです(笑)。
佐藤:
僕が見ていた景色で言うと、西村くんはやり方を完全に変えたというよりは、「自分がやってきたことを、さらにスケールさせるためにアップデートした」という表現が正しい気がします。気合と根性で活動量を担保するという西村くんの唯一無二のエッジや強みはそのままに、AIを活用することでその強度の質をさらに高めた。だからこそ、より大きな成果につながったんじゃないかなと思います。
西村:
本当にナレッジが多すぎました(笑)。最終的に120件くらいあったと思います。ザーッと並んでいる中から、今の自分がインプットできることは何だろう、と探していく感じでした。
佐藤:
ナレッジの対象はAI活用だけに限定していませんでした。生産性を上げたり、成果を最大化させたりするために必要なことなら何でもOKとしていたんです。そうしたら、思った以上に波及して。
西村:
「早起き」のナレッジとかもありましたよね(笑)。
佐藤:
そうそう(笑)。西村くんのナレッジの熱に当てられて、僕も感化されて毎朝7時半に出社するようになりましたから。AIとは関係ないですが、そういったナレッジもすごく良かった。
西村:
「こんなことでもいいんだ」って思えましたよね。
田本:
それ、すごく大事だよね。我々2人だけでトップダウンでやっていたら、絶対にこうはならなかった。西村くんたちのように現場でモメンタムをつくってくれるメンバーがいて、「早起きって良くない?」みたいな発信に対して、僕らが「それいいね! 俺もやる!」って乗っかっていく。そうやって、いい意味で発信のハードルを下げていくことができた。
早起きだけではなく、他のナレッジもメンバーが実行の強度を持ち、そしてそれを前向きにまずはやってみる、という文化があったからこそだと思います。
西村:
「これでもいいんだよ」という土壌をつくれた、という自負はありますね。

西村:
一番は、AIとの付き合い方が分かってきたことですね。以前は、AIが全部やってくれる、みたいなイメージだったんです。メール文をつくるなら、プロンプトを入れたら出てきたものをそのまま全部コピペして完成する、みたいな。けど、それだと「なんか一部合わないな」「使いこなせていないな」と感じてしまっていて。
でもプロジェクトを通じて、全部を置き換える必要はないんだ、と気づきました。たとえば、この部分だけは使えるな、とか。AIでうまく転用できるところと、ここは人力で自分がやった方がいいところ。その住み分けの「手触り感」を得られたのが、すごく大きかったです。
西村:
まさに、そうです!
佐藤:
すごく分かります。自分のエッジをどれだけ活かすか。そのためにAIが存在している気がします。僕だったら、お客さんと直接コミュニケーションを取るのは得意だけど、文章を考えるのは苦手。そういう、自分の得意を伸ばすために補うべき作業をAIが担ってくれる。そうすれば、僕らは本当に活躍すべき能力をどんどん伸ばしていける。このプロジェクトで、僕自身もそのことに気づかされました。
負けたことが、組織を強くした
田本:
実は、プロジェクト期間中の成果、具体的にはパイプラインの創出額は、目標未達で終わってしまったんです。ただ一方で、活動量は120%近くまで伸びていました。
田本:
はい。ただ、この取り組みの効果が、次の四半期で圧倒的な形で現れました。それまで未達だったのが、100%達成できるようになったんです。まさに「努力と成果のタイムラグ」ですね。やって良かったなと心から思っています。
佐藤:
僕は「負けたこと」がすごく重要だったと思っています。負けをぼかさずに、なぜ負けたのかをちゃんと分析して、じゃあ勝つためにどうするかを考え抜く。負けたけれど、活動量は大事だよね、でも活動量だけじゃダメなんだ、という学びがあった。やった結果として「こうしなきゃいけない」という説得力や腹落ち感が、組織全体ですごく高まったと感じています。

佐藤:
ユーザベースの「34の約束(※)」の中に、「現状の延長で限界を描くのではなく、やり方自体を変える」というものがあります。僕はこれがすごく好きで。今のISは、まさにこのままだと勝てないと思っています。

34の約束より
34の約束:ユーザベースのバリュー(The 7 Values)を、人種・国籍・宗教など多様なバックグラウンドを持つメンバーが、言語の壁・習慣の壁を乗り越え共通の理解を持てるようブレークダウンしたもの。冊子になっており入社時に配られる。
佐藤:
やり方自体を、根本から変えていかないといけない。AIを活用することで、これまでISにはできないと勝手に思っていたことができるようになるはずです。役割や自分の動き方自体を、どんどんアップデートしていきたいですね。
田本:
磨央くんが言ってくれたことに尽きますが、付け加えるなら、米国ではすでにSDR(Sales Development Representative/インサイドセールスの一種)の架電業務がAIに置き換わり始めています。知識量、いわゆるIQの部分では、いずれAIに勝てない時代が来る。
そうなった時に我々に求められるのは、EQ、つまり感情的な知性です。顧客接点が最も多いISだからこそ、熱量やモメンタムを持ってお客様と向き合える。その価値は、AI時代においてますます重要になっていくはずです。顔が見えないコミュニケーションだからこそ、人の力が試される。すごく面白い挑戦だと思っています。
西村:
いや、もう、最高です! 私みたいな「気合と根性」タイプでも変われたので、きっと誰でもできると思います。……まあ、気合と根性は相変わらず大切にしていますけどね(笑)。でも、AIに全部お任せするんじゃなくて、自分の武器をさらに磨くために使う。その感覚がやっと掴めました。

編集後記
今回の記事は、にしむー(西村のあだ名)から「レッドロックで1位を獲ったので、取材よろしくお願いします!」と言われたところ始まりました。たもち(田本のあだ名)と磨央くんからまだ何も聞いていなかった私は、「え? 何の話? レッドロックって何??」と戸惑いまくったのを覚えています(笑)。
その後、どんな内容にするのか、何を伝えたいのかをすり合わせていくうちに、「めっちゃいいじゃん!」と。生成AIは進化が早く、現時点でオペレーションをガチガチに固めるのは違うよね、という視点にも共感しましたし、組織内のナレッジシェアをどうするか? という問いに対する良いヒントをもらった感覚です。私もNotionのナレッジDBを覗きにいってみます!