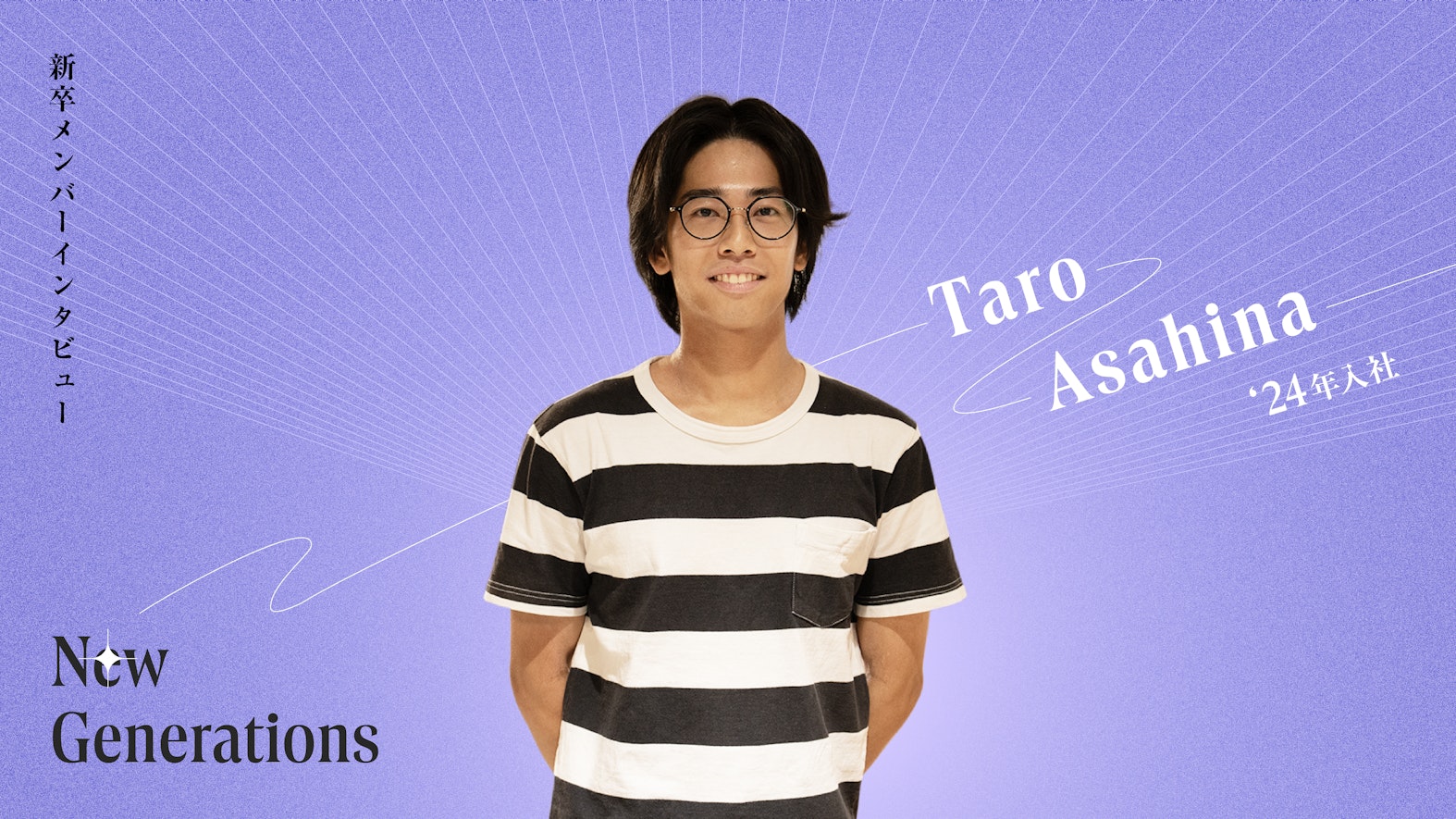「喋りながら開発できるの!?」常時ペアプロというカルチャーへの衝撃
僕とユーザベースの出会いは、大学3年生のときに参加した「TECH BASE Okinawa」というイベントです。ただ、僕は参加者としてではなく、大学から案内が来たボランティアスタッフとして関わったんです。
そこで一番印象に残っているのが、イベント後の打ち上げでした。ボランティアスタッフも一緒に、居酒屋に連れて行ってもらったんです。その時に席が隣になったのが、CTOの林さん(林 尚之/執行役員 スピーダ事業CTO)でした。
そこで林さんから「うちの組織はXP(エクストリーム・プログラミング)をやっていて、常時ペアプロで開発しているんだよ」という話を聞いて。エンジニアって、ひとりで黙々と仕事をして、最後にレビューしてもらう、みたいなイメージがあったので、すごく衝撃を受けました。


そうなんです。僕はもともと喋るのが好きなので、誰かと喋りながら、ひとつのPCで2人で開発できるっていうスタイルが「すごいな」って。プロダクトそのものというより、そのプロダクトチームのカルチャーに強く惹かれて、「この会社、いいな」と思ったのが最初のキッカケですね。

大学では情報工学を専攻していて、プログラミングを活かしたいと思って情報系の就職先を探していました。ベンチャーのSaaS企業やSIer、あとはサイバーエージェントのようなメガベンチャーも受けていました。といっても全部で8社くらいしか受けてないんですけど。
間違いないです。林さんと話して聞いた「常時ペアプロ」というのが、どうしても頭から離れなくて。若いうちに、いわばシニアクラスのエンジニアの方と付きっきりでプログラミングができる環境って、ひとりでやるよりもどう考えても成長できるじゃないですか。成長したいという気持ちが強かった僕にとって、そこが一番の魅力でした。
ギャップはゼロ。選考インターンで「ありのまま」を体験
それが、全くなかったんです。というのも、プロダクトチームの選考過程には、2〜3週間のインターンシップがあるんですよ。1日8時間、社員の方と全く同じチームにポンと入れられて、「じゃあ、どうぞ」みたいな感じで。
なので、インターンでやっていたことと、入社後にやっていることは、本当に何も変わらないんです。だから入社前後のギャップは全くありませんでした。
正直、Webのソフトウェアエンジニアとしての経験はなかったので、技術力はほぼゼロからのスタートでした。それでも内定をいただけたのは、やっぱりバリューに合っていたからだと後から聞きました。
プロダクトチームには「シェアドリーダーシップ」という考え方があって、チームの中に特定のリーダーを置いていないんです。新卒だろうが、技術力の高いシニアエンジニアだろうが関係なく、自分で考えて動いて、ボールを奪いに行く姿勢が求められます。インターンの時から、指示待ちにならずに「これやっときますよ」みたいに、自然にボールを拾いに行けていたのが良かったのかもしれません。

いえ、初めてだったので最初はめちゃくちゃ緊張しました。何から話していいか分からないし(笑)。ペアプロには、実際にコードを打つ「ドライバー」と、そのコードを見ながら客観的にフィードバックをする「ナビゲーター」という役割があるんですが、理想は10秒とか30秒ごとに入れ替わりながら、2人でひとつの頭脳のように開発を進めていく状態なんです。
先輩を前にして緊張はしましたが、「ここでキーボードを打てなきゃ始まらない」と思って、とにかく先輩からキーボードを奪うくらいの気持ちで前のめりに取り組んでいました。そういう姿勢も評価してもらえたのかなと思います。
シニアの思考を隣で学ぶ。爆速で成長できるペアプロのリアル
はい、今は週5日で出社しています。オフィスに長い机があって、そこにみんなで集まって開発していますね。誰かがリモートワークする日は、全員が「Gather」というバーチャルオフィスに集まってペアプロをします。
やはり、エンジニアとしてできることが格段に増えました。技術的な引き出しが増えたことで、PdM(プロダクトマネージャー)のようなビジネスサイドのメンバーから「こういう機能がほしい」と言われたときに、「こうすればできますよ」と積極的に提案できるようになったのは大きな変化です。もともとコミュニケーションを取るのは好きなので、技術的な自信がつくことで、よりチームの前に立って動けるようになってきたと感じています。
本当にその通りです。どんどんやってみろ、という雰囲気ですね。もし間違っていたり、方向性が違ったりしても、周りのメンバーが「こういう方法もあるよ」とすぐにフォローしてくれます。だから、安心してチャレンジできます。
特にペアプロは成長の機会の宝庫です。たとえばインシデント(障害)が発生したとき、ひとりだったらどうしていいか分からず慌ててしまうと思うんです。でも、隣に先輩がいて一緒に対応してくれるので、「こういうときは、こういう部分を見て、ここに連絡するんだな」という一連の流れを実践で学べます。一度経験すれば、次は自分で動けるようになる。このサイクルが、ものすごいスピードで成長させてくれている感覚があります。

昨年、エキスパートリサーチの「Flash Opinion」という機能で、一度に複数の質問を送れるようにする開発を担当しました。それまでは1回の依頼で1つの質問しかできなかったんですが、最大5つまでまとめて送れるようにしたんです。
リリースした翌月から、その機能の利用チケット数がグラフで見て明らかにボンッと伸びて。「この機能、めちゃくちゃ効果があったんだ!」と実感できました。自分たちのつくったものがお客様にたくさん使われて、会社の売上に直接貢献しているのを感じられたときは、本当に嬉しかったですね。
ドキュメントは残さない。人が流動することで知識を伝搬させる
はい。プロダクトチームには「チームシャッフル」という制度があって、短ければ3ヵ月、長くても1年くらいで担当するプロダクトやチームが変わるんです。知識が特定の人に偏る「属人化」を防いで、組織全体に知識を伝搬させるのが目的です。僕もFlash Opinionのチームに1年ほどいたので、今年の4月からSpeeda AI Agentの立ち上げメンバーとして新しいチームに移りました。
はい、もう全く違います。使うプログラミング言語からして違いました。技術選定の際に、最終的に全く触ったことのない言語を採用することになり、「え!?」ってなりましたけど(笑)。
でも、これもProduct Teamの考え方のひとつで、常に新しい技術を積極的に取り入れることで、変化に強い組織をつくっているんです。最初は戸惑いましたが、ペアプロをしながら先輩に教えてもらったり、自分で勉強したりして、今では少しずつ書けるようになってきました。なんとかなるもんです。

いえ、むしろ逆です。ドキュメントは基本的に残さない文化なんです。
ドキュメントって、書いた人がいなくなったり、更新が止まったりすると、いつの情報か分からなくなって、かえって混乱を招くことがありますよね。それなら、ドキュメントに頼るのではなく、人の入れ替えを活発にして、口頭で知識を伝えていった方が確実だ、という考え方なんです。
だから、分からないことがあれば、詳しい人に直接聞きに行く。「聞く前に調べろ」ではなく、「迷ったら聞きに行け」が僕らのスタイルです。その方が問題解決も早いし、知識も伝搬する。一石二鳥なんです。
「迷ったら挑戦する道を選ぶ」。2年目で新規事業の立ち上げへ
「迷ったら挑戦する道を選ぶ」ですね。僕自身のこれまでの人生を振り返っても、どっちでもいいなと迷ったときに、少し難しかったり面倒だったりする方を選んだ方が、後から「こっちを選んで良かったな」と思うことが多かったんです。このバリューは、自分の経験則とも合っていて、すごくしっくりきています。
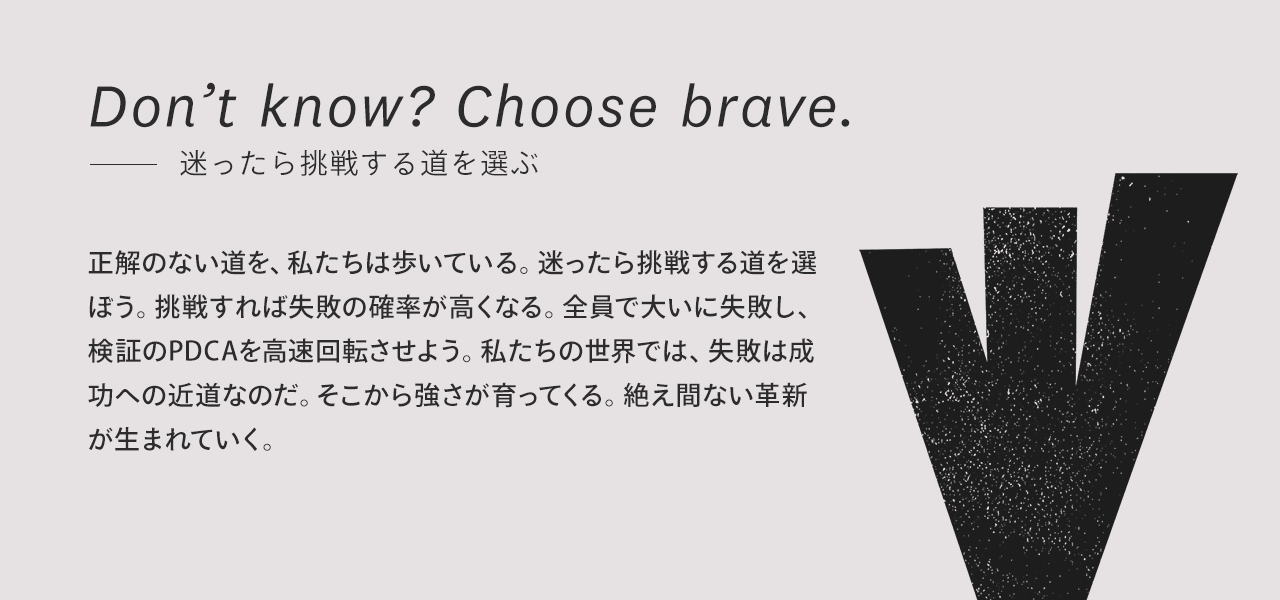
まさに、今のSpeeda AI Agentチームへの異動がそうでした。2年目になったタイミングで、ゼロから立ち上げる新規事業に誘われたんです。正直、「2年目の自分に務まるのか?」という不安はありました。でも、これは間違いなくチャンスだと思って、挑戦する道を選びました。
結果として、優秀なメンバーたちと一緒に新規事業の立ち上げという貴重な経験ができています。あのとき、慣れた環境に留まるのではなく、チャレンジして本当に良かったなと思っています。
自律し、自分でボールを奪いに行ける人
やはり、自律していて、自分でどんどんボールを奪いに行ける人だと思います。年次や役職に関係なく、気づいたことがあれば手を挙げて、言うべきことはしっかり言う。そういう積極性が求められますし、それができる人にとっては最高の環境だと思います。
同期は14人いるんですけど、めちゃくちゃ仲が良いです。この間も、みんなで千葉の一宮にペンションを借りて泊まりに行きました。まだ誰も辞めていないのも、ちょっとした自慢ですね(笑)。
エンジニアもレベニューサイドのメンバーも垣根なく仲が良くて、飲みに行くと気づいたら仕事の話で熱く語り合っている、なんてこともよくあります。みんなそれぞれ熱い夢を持っていて、素直で、本当に「入るべくして入った」人たちだなと感じますね。
「Speeda AI Agentで世界を変える」ことです。今、まさに僕が開発しているこのプロダクトで、世の中を大きく変えたいと思っています。AIにはハルシネーション(事実に基づかない情報を生成する現象)という課題がありますが、ユーザベースが長年培ってきた信頼性の高いデータを基盤に使うことで、そのリスクを限りなく下げることができます。信頼できるデータとAIの力を掛け合わせれば、とてつもなく便利なものができる。これは絶対に勝てる! と確信しています。
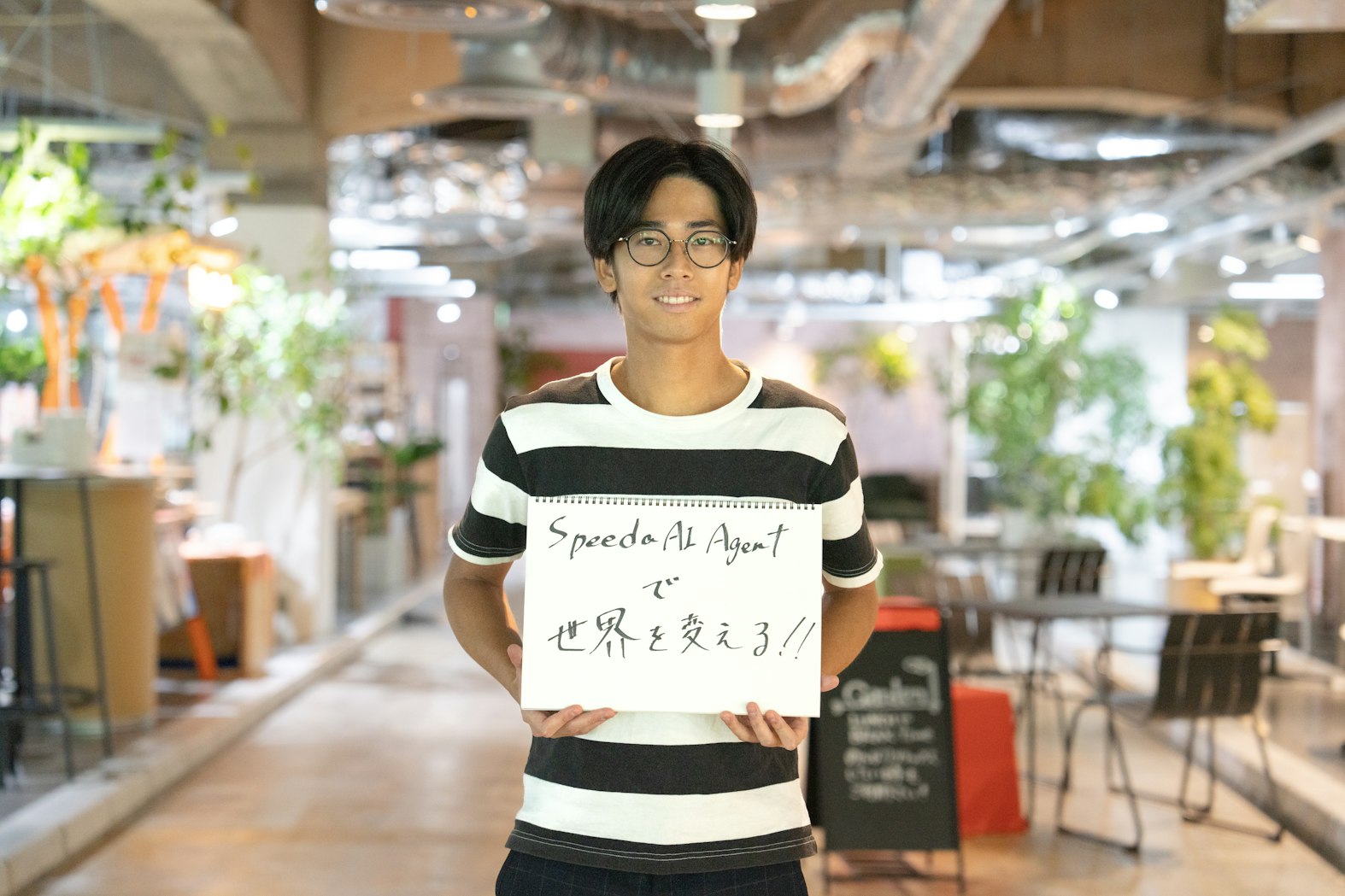
編集後記
「Speedaって常時ペアプロやっているんですよね!」とよく聞かれるものの、具体的にどんなふうにやっているのかイマイチ分かっていなかったんですが、今回のインタビューでだいぶイメージできるようになりました! 朝比奈くんがユーザベースを知るキッカケになった「Tech BASE Okinawa」には私も取材に行っていたんですが、あの打ち上げにいたボランティアスタッフから社員として入ってくれる人がいたなんて、なんだか感慨深いです。
ちなみに、ユーザベースで成し遂げたいWill、誤字があったとのことで撮影し直したんですが、その間に髪を切りに行ったため、若干見た目が変わっています(笑)。