「記念受験」から始まったキャリア
そうなんです。実家が会社をやっているので、将来的にはそこでもいいかなと思っていましたし、当時、地元のゲーム系ベンチャーでエンジニアとしてアルバイトをしていて、そこの社長から「ぜひ来てくれ」という話もあったんです。だから、就活しなくても生きていけるかな、当時のエンジニアは本当に売り手市場だったので、何とでもなるかな、という甘い考えでしたね(笑)。
でも、大学院1年の12月末くらいに、「院まで行って就活しないのはさすがにアレだから、記念でやっとくか」みたいな感じで、就活エージェントに登録したんです。

はい(笑)。そこで「Web系のサービスをやりたいです」と伝えたら、「好きなサービスはなんですか?」と聞かれて。個人的にNewsPicksを使っていたので、そう答えたら「募集ありますよ、受けますか?」と。それが最初のきっかけです。
NewsPicksは大学4年生くらいからです。先輩が使っているのを見て、動画コンテンツを見せてもらったら面白くて、自分でも見るようになりました。僕がいた鹿児島だと、そもそも大人でも使っている人が少なかったので、知るきっかけがほとんどなくて。たまたまその先輩がいたから知れた、という感じですね。
ユーザーの声が届かないもどかしさ
大学3年生の時です。もともと情報工学の道に進んだのは、パソコンが好きだったから、という雑な理由なんですけど(笑)。やってみたら楽しかったので、仕事として考えるのはありかな、と。そこからアルバイトを始めて、やっぱり問題解決をするのは楽しいな、と感じるようになりました。
はい。身近な友だちの困りごとを解決するようなアプリをつくるのが好きでした。たとえば、僕はゲームが好きなんですけど、うまくできた瞬間の10秒くらいの動画を仲間内で共有する文化があって。でも、当時使っていた通話アプリのDiscordは容量制限で2秒くらいの動画しか上げられなかったんです。
それで、動画をアップロードしたらURLが生成されて、それを共有すればWebで見られる、という簡単な動画共有アプリをつくりました。仲間内で数十人くらいが使ってくれて、「やったぜ」って。それがひとつの成功体験になりました。エンジニアの仕事は楽しいんじゃないか、と思い始めたきっかけのひとつですね。

考えていました。でも、僕がやっていたのが、漫画アプリの広告で流れてくるようなゲームをひたすらつくって市場に出して、流行らなかったら即廃止、というサイクルを繰り返すような仕事だったんです。
そうなると、開発者としては、せっかくユーザーからコメントをもらっても、それに対する改善は行われずにサービスが終わってしまう。それってつまらないなって。上の人に「せっかく意見があるんだから、改善すればまだ行けるんじゃないですか?」と言ってみたんですけど、「いや、そういうものじゃないから」と返されてしまって。そこで、ちょっと違うかな、と感じるようになりました。
入社の決め手は「楽しそうな社員」とThe 7 Values
軽いノリで受け始めたんですけど、選考過程でプロダクトを開発しているエンジニアの方々と面接する機会があって。話していると、すごく楽しそうだったんです。
僕の周りには当時、仕事を生きがいにして「仕事が楽しい」と思えている社会人があまりいないように感じていたんです。だから、それがすごく新鮮で。「この人たち、なんでこんなに楽しそうに仕事できてるんだろう?」って、興味をそそられました。
やっぱり、ゲーム会社での経験があったので、「ユーザーの声をちゃんと聞きたい」という思いが強くありました。面接でその話をしたら、エンジニアの方がThe 7 Valuesについて深く語ってくれて。「あ、自分のやりたいこととマッチしてるな」と思えたのが決め手ですね。ここに1回行ってみて、ダメだったらまた変えればいいや、くらいの気持ちでしたけど(苦笑)。

いえ、全く(笑)。SREの勉強会とかに行っても「1年目からSREやってるの、おかしくない?」って言われるんですけど、全然希望していたわけではなくて。バイトでやっていたのもフロントエンドが多かったので、インフラはほとんど触ったことがありませんでした。いきなりSREに配属されて、「SREって何ですか?」というところから始まったのを覚えています。
後から聞いた話ですが、当時の僕は用意されたクラスやライブラリの処理を組み立てるだけの開発が中心で、技術の根本を理解していなかったんです。だから、事業部でいきなり開発するより、まずはSREチームで技術的な知識をしっかりつけて成長させよう、という会社の意図があったみたいです。
1年目の大抜擢が生んだ「当事者意識」
SREの“ユーザー”は、社内のエンジニアや社内システムを使う人たちになるんですが、彼らとの距離がすごく近いんです。要望が直接僕のところに来て、それを自分の裁量でどんどんさばいていける。これはすごくやりがいがあって、めちゃくちゃ楽しいなと思いながらやっています。
1年目に、NewsPicksのカスタマーサポートチームが使う「Watson」という社内システムのリアーキテクチャ(再設計)を任された時ですね。当時のSREリーダーだった安藤さん(安藤 裕紀/NewsPicks CTO)から「樋渡さんの仕事にしたいからやってみて」とプロジェクトを任せてもらって。
それをやり遂げたことで、プライドというか、「これは僕の仕事だ」という意識が芽生えました。それからは、Slackで誰かが困っていそうだったら、スレッドに突っ込んでいって「これやりますか?」みたいに、自分からガンガン仕事を取りにいくようになった。それが大きな変化でしたね。
なかったですね。1年目の頃は目の前の仕事を片付けるので手いっぱいでしたし、メンションも僕個人ではなくSREのグループ宛に来て、それを先輩たちがさばいて、僕にもできそうなものを振ってくれる、という感じだったので。でも、プライドが芽生えてからは「僕に仕事をくれ」と、自分から取りにいくようになりました。

コミュニケーションを取りたい、というのが一番の理由です。SREは、どうしても事業部との絡みが少なかったり、相談を受けてから仕事が始まることが多かったりして、普段の業務で他チームとのコミュニケーションがあまり発生しないんです。
同期には事業部側で働いているメンバーもいて、彼らはエンジニア以外のデザイナーやセールスとも関わっている。そうすると、エンジニアリング以外の経験値もどんどん溜まっていきますよね。SREにいると、どうしてもその機会は少ない。
それで意識的にコミュニケーションを取りに行こうと思って。いきなりセールスに絡んでも仕方ないので、その前段階として、まずは顔を覚えてもらおう、と。とりあえずオフィスに行って、「あそこに座ってる人だ」くらいの認識でも持ってもらえれば、それが関係構築の第一段階になるかな、というモチベーションで出社しています。
「迷ったら挑戦」を後押しする文化
エンジニアとして、守備範囲をすごく広げられる点ですね。「SREチームだからこれだけやっておいて」ということは全くなくて、NewsPicksのプロダクト全体を見て、課題があると思えば、やりたい改善に挑戦できる。シニアエンジニアたちがサポートしてくれる環境もあるので、技術領域に縛られないという意味で、すごく自由だなと感じます。
ただし、やりたいと思って自分で突っ込んだ以上は、やり切らないといけないし、その後の責任も自分が取らないといけない。自分が開発したものなんだから、自分が責任を持つ、というのはエンジニアとしてのプライドでもある。守備範囲を広げた分、そこに付随する責任を自分で持つ。そこに自由と責任を感じますね。
僕は技術そのものよりも、課題解決に興味があるタイプなんです。なので、SREチームのタスクの中で、自分が今までやったことのないものがあったら、「このタスク、僕にください」と巻き取るようにしています。そうすると、その課題を解決するために、ゼロから新しい技術を学ばざるを得なくなる。そうやって、できることを増やしてきました。
挑戦しやすい環境というか、何かあってもシニアの先輩たちが助けてくれる、という信頼感があります。本格的にまずいことになる前に、絶対助けてくれるだろう、と。監視されているわけじゃないんですけど(笑)。
過干渉なわけではなく、でもちゃんと見てくれている。だから、失敗しないように萎縮するより、のびのびと「とりあえずやるか」と思える。すごく安心感のあるチームです。

それは、1年目の時のリーダーだった安藤さんのおかげですね。僕はもともと質問するのが苦手だったんですが、安藤さんは朝会で知らない単語が出てくるたびに「はい、樋渡さんこれ説明して」と僕に振るんです。それを1年目、ずっとやらされて。
はい(笑)。質問されるのが前提になると、「やばい、わかんない、調べなきゃ」ってなりますよね。そのおかげで、わからないことをわからないままにしない習慣が身につきました。今思うと、ありがたいですね。
そうですね。入社する前は「できるかわからないから、やらない」というタイプだったんです。でも、SREに入ったら「できないのは当たり前だからやれよ」という文化で。実際にやってみたらサポートもしてもらえて、やりきったら評価もされる。その成功体験を積む中で、自信がついてきて、「やればできるんじゃないか」というマインドに変わりました。
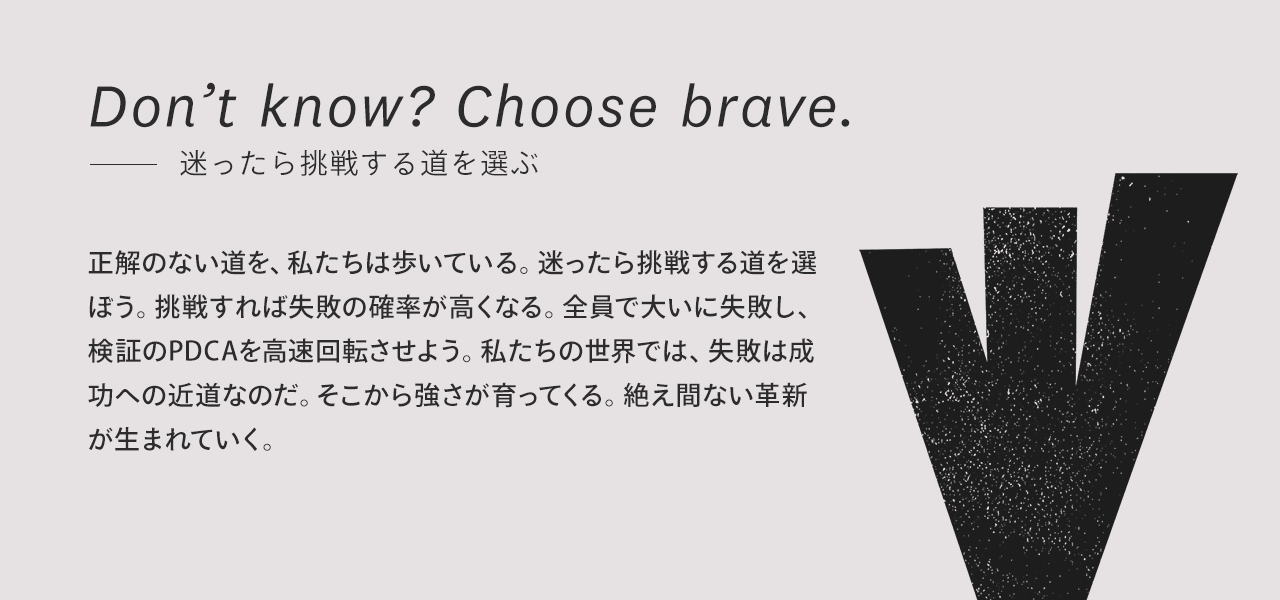
ユーザベースで働く上で大切な「主体性」
うーん、言葉が強くなってしまいますが、「主体性を持つのがそもそも嫌だ」という人でしょうか。決められたことを、決められた通りにだけやりたい、という人。
ユーザベースでは、何かタスクを振られたとしても、まず課題を理解したうえで「あなたはどうしたいの?」「どう解決していくの?」という部分を求められると感じています。上司はきっと正解を持っているんでしょうけど、その正解をただ実行するロボットではなく、自分なりに「こうだと思いました」という意見を出すところから始める。そのプロセスを大事にしているんだと思います。
そうですね。だから、「正解持ってるなら早く教えてくれよ」みたいなタイプの人は、結構しんどくなっちゃうかもしれない。社内の人たちと合わないだろうな、と思います。
「ユーザーの声を聞き、NewsPicksを成長させる」。これですね。今はSREという立場ですが、いつかはちゃんとユーザーの声を聞いて、プロダクトを成長させることに関わっていきたいです。
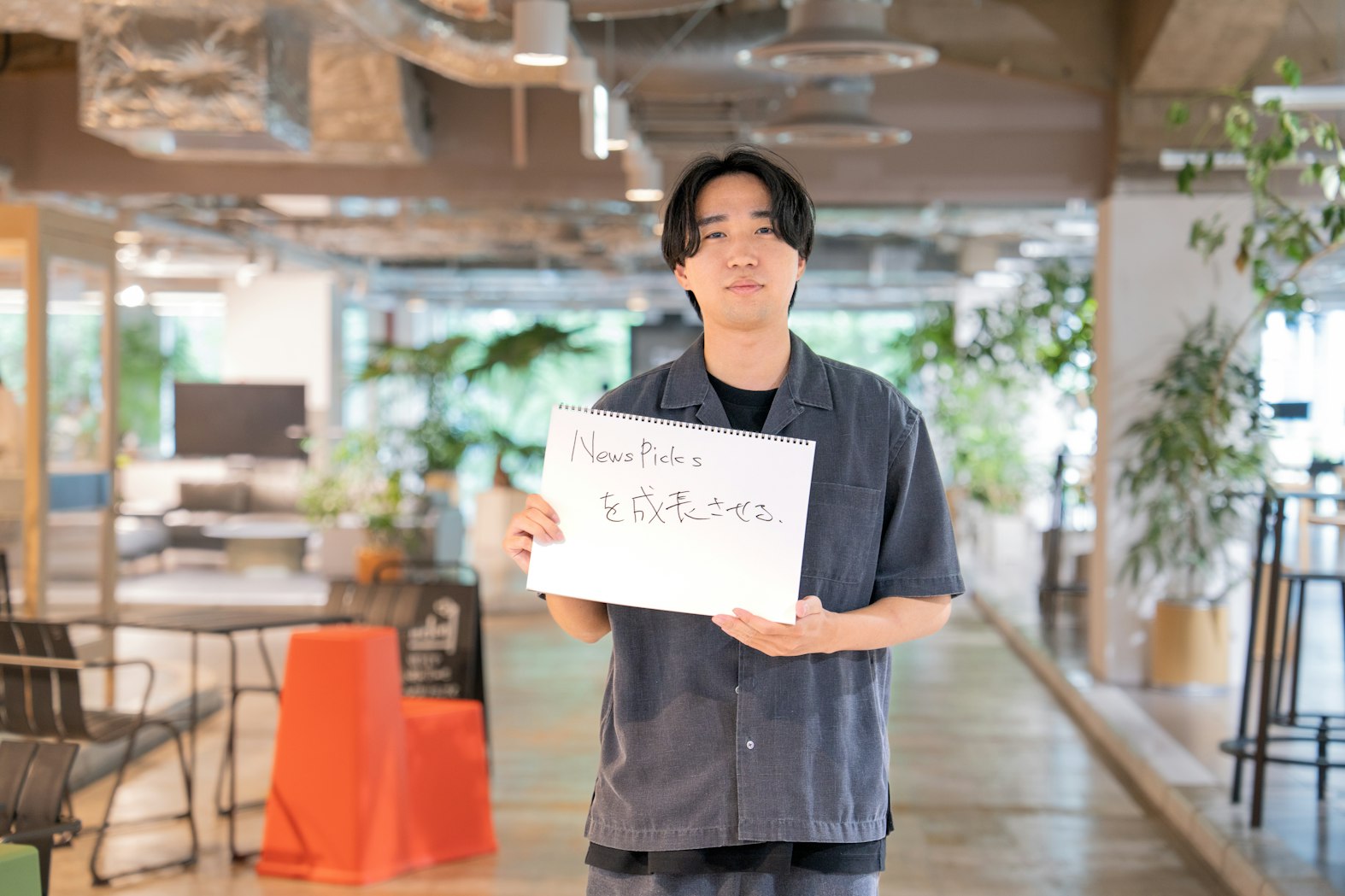
編集後記
インタビュー冒頭で「記念受験」的に応募した、というエピソードを聞いてちょっと心配になりましたが(笑)、「これは自分の仕事だ」というプライドが生まれた話を聞いて、素敵だなぁと思いました。樋渡くんに限らず、2024年入社の新卒メンバーは、好きなバリューとして「迷ったら挑戦する道を選ぶ」を挙げる人が多い印象です。課題解決が好き、コミュニケーションを取りたい、という樋渡くん、今後の成長もめちゃくちゃ楽しみです!








