「我こそはユーザベース!」と思って好きにやってほしい
新野 良介(以下「新野」):
どうもこうも見ていないです(笑)。冷たく言うわけじゃないんだけど、僕がチームのみなと仕事をしていた時は、素晴らしい場所で素晴らしい仲間と仕事をしたいという思いで、自分のために、当事者として必死でそれを整えてきただけなんですよね。

だから振り返ってみれば、その頃のことをどうこう評価もできるかもしれないけど、今の組織への評価の良し悪しは、いまのチームのメンバーが一般論や総論じゃなくて、自分にとって素晴らしい場所なのか、素晴らしい場所にし続けるだけの愛すべき場所なのか、という視点だけが大事です。だから、みんな好きにしてほしいです。
新野:
そうそう。1人ひとりが、「我こそはユーザベースだ」と思って好きにやってほしい。もうそれだけです(笑)。
新野:
極端に言えば、私がユーザベースで、ユーザベースが私だから、という感覚。
だって、自分からみれば、組織のための手段として自分があるのじゃなくて、自分のための手段として組織があるわけだから、「自分のための組織」。
だから人数が多くなっちゃったとか、大企業っぽくなっちゃったとか、なんだっていいんです。大事なのは、みんなが「自分が所属する場」を、どれだけ「自分が愛せる場」にすることに本気になれるかどうか。それが組織の進化だと思います。
でも組織論となると、枠の議論が先になる気がするんです。1000年も生き残った組織なんてないから、そりゃミッションや使命も終えますよ、終えたって全然問題ないと思いませんか。もちろん、ユーザベースがなくなってほしくないとは思っていますけど(笑)。
宇田川 元一氏(以下「宇田川」):
とても共感します。本当にその通りだなと思ったのが、組織は本来、目的を達成する為の手段なんです。目的が達成されたら解散するはず。なのに、なぜ組織は続こうとするのかという議論は、組織論でも初期から研究されていました。
フィリップ・セルズニックという組織社会学者の議論なのですが、なぜ組織が続くのかと言うと、それはなにかの価値観、期待にコミットする、絡め取られるからだというのですね。だから、無理に目的を作ろうとする。そうすると、そもそもやろうとしていたことからどんどんズレてくる。
経営者の立場からすれば、絡め取ってしまったほうが楽なのかもしれない。けれど、そうじゃないんだと。組織が絡め取ってくるならば、その組織は変わらなければならないわけですね。
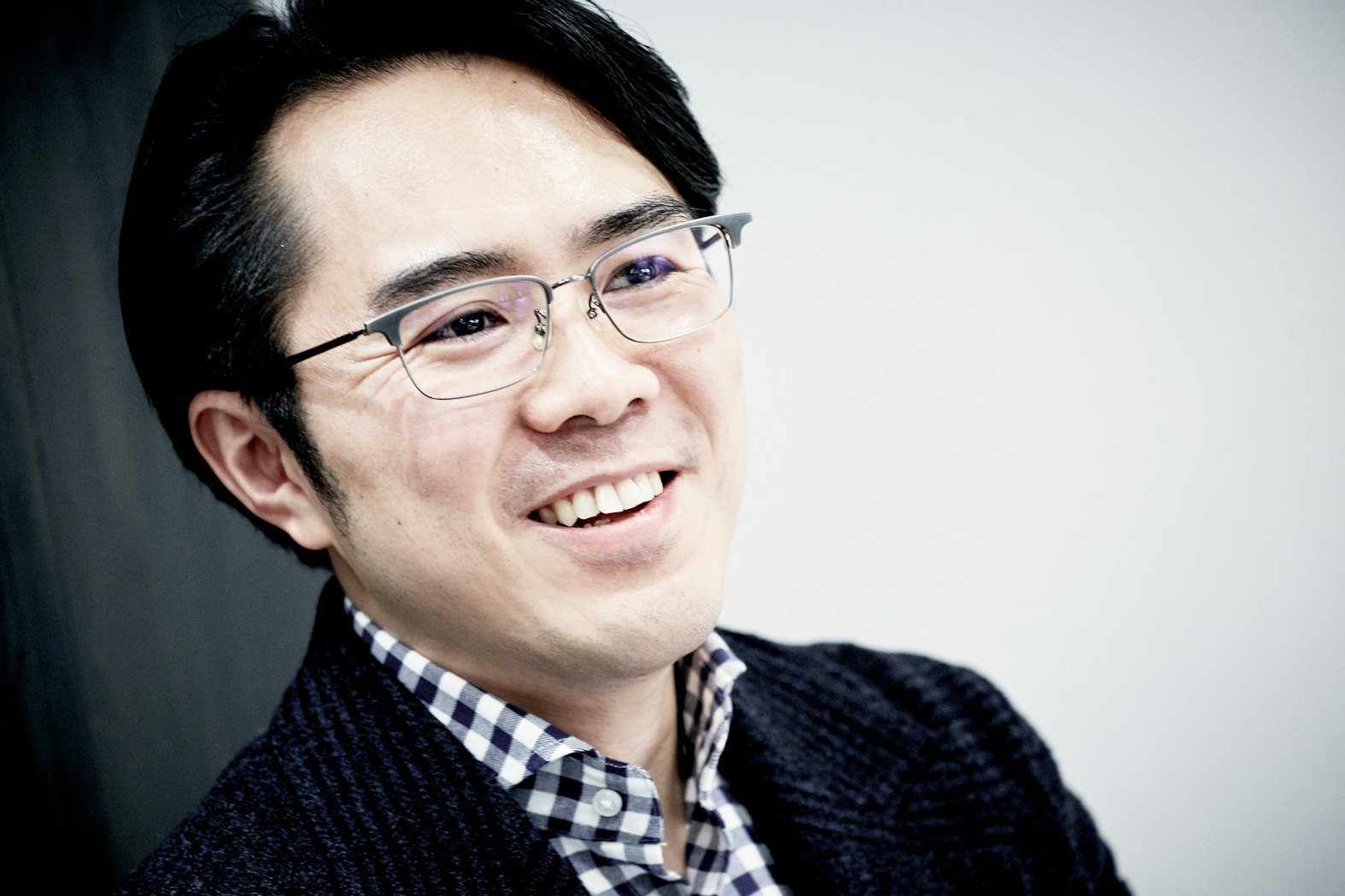
ロックバンドのように組織は解散していい
新野:
僕の考える「組織と個人」の関係は、アメリカ建国の精神と似ているんじゃないかな、と思います。
例えば、とあるお父さんとお母さんが、貴族からの圧政から逃れて、子供たちにはもっといい暮らしをさせたいと奮起したから、メイフラワー号に乗ってフロンティアを目指すわけです。でも必死でたどり着いてみたら森ばかりで、本当に大丈夫かと不安になったそばから、インディアンの矢がビュッと飛んできたりして。「ええっ、ここ、大丈夫!?」みたいな(笑)。
そこで必死で動いて、腕まくりして未踏の大陸を開拓していった人たちが、アメリカにはつい250年前にいます。当然ですけど、彼らには圧倒的な当事者意識がありましたよね。「国があって私がいる」じゃなくて、「私があって国がある」という意識です。
新野:
いや、ロックバンドでも一緒です。ボーカルをやりたい僕とギターをやりたいあなたがいるからバンドを組むじゃないですか。それで自分たちの思う最高の音楽をつくって、「俺たち音楽性違うな」と思ったら解散して次に行くっていう。組織だって、究極的には個を主軸に、自分本位にあっていいと思う。
組織の枠に注目して自分本位になり切れていないから「俺ひとりが立ち向かっても変わらないや」なんて言う風に、組織への無力感が生まれる。これこそが大企業病の本当の姿だと考えています。
宇田川:
多くの企業でも、ビジョンステートメントやミッションはよく考えてつくられているとは思いますが、感じのいい綺麗事みたいな言葉になってしまうことがとても多い。
すると高尚な目標に対して当事者になれない社員が出てくる、という現象が生まれがちです。組織の目指す風景の中に、自分がいられないと感じてしまう。

新野:
その通りだと思います。当事者として実践しなければ、結局、組織の劣化が止まらなくなってしまう。みんなが感じているように、組織は何も手を加えないとどんどん組織の性格と個人の生き方は離れていってしまうんです。
自分以外にも働ける誰かがいて、誰かが作ってくれた歴史があって、無力で小さな私なんて、みんなに合わせたほうが全体最適だ、というような考えです。自分のことを組織に預けきってしまうんですよ。
「ユーザベースと言ったら私と私の仲間のことだ」と思えば、自分がどう生きたいか、自分に帰属します。
ストーリーを他人任せにして、「会社が自分を幸せにしてくれる」と考えているとしたら、既にフォロワーに成り下がっていて当事者じゃないわけです。
これは、所属する組織で人数が増えるとか、大企業になるとか、そんなことに関係ありません。むしろ10人の組織でも起きるし、逆に1万人の組織でもイノベーティブな企業はあるはずです。
宇田川:
なるほど、だから組織という枠を「どうもこうも見ていない」んですね。
新野:
むしろ大事なのは、「選んでるのはこっちだよ」という1人ひとりの意識。それが前提にないと、他人から考えを押し付けられたり、他人からの評価が気になってしまって、どんなシステムを選ぼうとどこかで満足できなくなるはずです。
自分の苦労を受け入れることで「当事者」になれる
宇田川:
わかります。その問題の解決には、結局のところ「どうやって当事者でいるか」という原動力が必要になりますよね。組織に入ると、なおさら個人としての意識が薄れていってしまいがちです。新野さんは、当事者であることをどのように捉えているんですか?

新野:
自分のしたい生き方をもって、ここなら叶えられると合理的な期待をして飛び込むことですね。「やらされている」ではなく、知った上で「いい苦労」をする。それこそが当事者として組織に属するということではないかと思います。
新野:どうせ苦労をするならば、「いい苦労をしたい」という気持ちが、僕が当事者であるための原動力です。つまり、自分の生き方の実現ために、組織の一員として苦労を引き受けて、みなと力をあわせて実現する。
それに、「自分の生き方」が先にあると言ったけれど、そもそも他者と渡り合うことでしか自己意識は生まれないはずです。人は他者からのフィードバックに晒されてはじめて、その反射として自己意識が形成される。
いい苦労をすると、それだけ良い自己意識、自分の苦労を受け入れる物語を自分で紡ぐための材料が揃えられるはずなんです。
宇田川:
僕は、「当事者になる」とは自分の苦労を取り戻して受け入れることだと思うんですよ。
北海道にある精神障害ケアのコミュニティの「べてるの家」から僕はそのことをたくさん教えてもらいました。べてるの家では、自分の病気について、自分と仲間で研究して、病人としての人生ではなく、病気もある人生の当事者として生きていくことを目指しています。
普通お医者さんからすれば「幻聴は病気」だから聞こえないようにしたいですよね。でも幻聴が表出して病気と診断されるけれど、本当に当人が対処したいのは、背後に抱え込んだ寂しさだったりする。幻聴も、たまに「お前、よくやってるよ」なんて励ましてくれたりするそうです(笑)。
こうして本人が病気を通して受け取った課題になんとか向き合い、寂しさに向き合うことで自分を取り戻す。こうして自分の苦労を受け入れることで、「病人」ではなくひとりの当事者になれるんです。

他者を通じて意味が発見される
宇田川:
そして、苦労を取り戻して自分の物語に紡ぎ直すとき、他者を必要とするんですよね。
旧約聖書創世記のヨセフの話を思い出します。ヨセフは兄たちに疎まれて、エジプトに奴隷として売られ、エジプトでも大変な苦労をしながらも、後に才覚を発揮してエジプトの王から行政の長に任命されるんです。
その頃に、父や兄たちの住むユダヤの地で飢饉が発生して、彼らがエジプトに移住させてくれとやってくる。その時に、自分を苦しめた兄たちに語った言葉が、「兄さん、私はヨセフです。私がここにいるのは、あなた達が売り飛ばしたからではなく、このような危機を助けるべく神が私を遣わしたのです」と語るんですね。
この話がすごいなと思うのは、自分の身に起きた不幸な出来事の意味が、自分の直面した様々な他者との出会いを通じて、意味のあるものへと変容していくことです。
仕事をしていて、上手くいかないことや辛く納得いかないことが出てきたとき、「これは何かの意味があるんだ」って信じるためには、他者を必要とするんだと思うんですよね。他者との出会いを通じて、何か新たな意味が萌芽的に見いだされてくる。それを語ることを通じて、「ああ、自分に起きたあの出来事はこういう意味だったのだ」とわかる。
これが物語の再編であり、自分というものが変わるということだと思うのですね。かつての自分の視野では見えていないものに、自分なりの意味を見出している。苦労に意味があると信じられることが、その人にとって力になるのだと思います。
新野:
まさにその通りですね。少し話は変わりますが、Googleの入社試験では不確実な環境への耐性を重要視して社員を選ぶそうです。大きい波に怖気付く人と、ワクワクする人だと、後者の方が今の変化の時代に強いですから。
でも一方で、Googleは社員の耐性を選別しているだけではなくて、入社したメンバーには「対話する時の安心感」も重視している。これは一見別のことのように見えて、僕にはひとつに感じます。
安心して他者と対話できることで「自分は他者に承認されている」という安心が生まれ、不確実な「良い苦労」に挑戦できる力が生まれるんだと考えます。
組織がすべきはこの挑戦へのサポートではないか、と。だから、僕はその安心感や他者への承認を奪うことが、組織としていちばん罪が重いと思うんですよ。
みんな同じように弱いから、「渦中」に友を助ける
新野:
自分が不完全なら相手も不完全、という言わば「性弱説」からはじまるものですね。自分が失敗するなら相手も失敗する。それを許して、他者を自分のように考えられるかどうかが、他者への承認だと思います。
当事者であるということも、みんな自分と同じように弱いという性弱説に立ち返ることだと思います。みな、自分と同じ弱い人間だからこそ、自分も相手も大事にしなければならない、という感覚です。それがないと、単に、強者のための自己責任論になってしまう。
「The 7 Values」でいえば「渦中の友を助ける」がまさにそうで、全員が弱いという認識になって初めて、「僕らはみな“迷える仔羊”じゃん。だから助けを求めて当然だぜ」と(笑)。
宇田川:
なんだかキリスト教的ですね。みんな同じ地面で迷っているぞ、互いに愛し合え、と。

新野:
友のことを、「基本的には自分の苦労を引き受けられる、力のある人だ」と尊重しつつも、誰ひとり全部自分でやり切れる人なんていませんよね。だから「やばい時にはすぐ駆けつけよう」と約束する。
自立しながらも、他者に開かれてるというか、他者とともに生きていることを前提にしている。
宇田川:
なるほど。一見、「会社が社員を信じている」だけの話のように見えますが、実は結構違いますよね。暑苦しい「自分たちはこういう人間として強い絆を持っていこう」という形式を守る話ではない。ここがとても僕は大切だと思いました。
大事なことは、普段はそれぞれ自立してやっていくことを目指す。だから、形式的なルールも必要があれば変える。でも、それは何か良い苦労をするためだからだと。その苦労の渦中の人を助けることも良い苦労ですよね。
なぜならば、自分も同じ弱さを持っているからで、他者を助けることを通じて自分を助けることも学ぶからです。逆に、日頃から形式的な強い絆があることで、かえって、その絆に縛られて、眼前の問題の渦中の人を助けることをためらってしまうかもしれない。
(前編の)冒頭でお話した当事者であれ、ということはこういうことなのだとよくわかります。つまり、当事者であるということは、良い苦労を引き受けていくことなのだと思うのですね。それは弱き人間である我々が、弱さを持ちながらも歩もうとすること、その中でその人の大切な苦労を誰かが取り上げてはならない、けれど、倒れているときは助けて苦労に向き合えるようにする、そういうことなのだなと思いました。
新野:
本当は誰だって恐る恐る歩いていると思うんです。だから、相手を自分と同じ人間として想像し、自分と同じように助けが必要なことを忘れない。たとえば、「梅田さんや稲垣さんはスーパーマンにみえるけど、必死にやっているだけだ。だからこそ、助けてあげなければ」って考えてほしいです。

新野:
「一番大事なことは相手の立場に立てることだ」って子供の頃から言われたけど、まさにそうだなと感じますね。相手の立場に立てる、これこそ、最高の感性であり知性である、つまり人間の可能性そのものだと思うのです。だから、それなくて、当事者意識だとか、イノベーティブな組織だとか、人間の生にとって意味のない議論だと思うんですよね。











