スタートダッシュの失敗、そして組織崩壊
2013年、ユーザベースは初の海外拠点として上海、香港、シンガポールにオフィスを開設すべく、創業者の新野良介と、当時、事業開発執行役員を務め、現在はUB Venturesの代表を務める岩澤脩の2人がシンガポールと香港に乗り込みました。
その1年前から、アジア市場に合わせてプロダクトを開発。何度も現地を訪れユーザーヒアリングを行うなど、初の海外進出に向け準備は万端でした。
しかし、そこから6ヶ月間、顧客開拓が全く進まない日々が続くことになってしまったのです。
原因は2つあり、1つは日本からリモートでのユーザーヒアリングに頼りプロダクトをつくったことで、全くエッジのないプロダクトとなっていたこと。現地のユーザーニーズを過度に取り入れたことによりプロダクトは総花的になり、自分たちが現地の肌感覚なく作った英語版プロダクトは現地ユーザーの感動を生むに至らなかったのです。
2つ目は、英語版SPEEDAにフォーカスしたプロダクトチームをつくれなかったこと。日本のプロダクトチームが日本から日本語版と英語版の両方を開発していたので、海外ユーザーからのフィードバックを即座に改善する体制が取れていませんでした。
そのため、ユーザーはSPEEDAの世界観は評価してくれても、お金を払ってまで導入するまでには至らず。当時を振り返り、岩澤は「結果が出ない毎日で、極限の状態が続いていた」と言います。
さらに、プロダクトの問題だけでなく、チーム崩壊も同時に起こりました。現地採用した立ち上げメンバーが次々と離脱していったのです。
原因は、即戦力を求めるあまり、ハイスキルな人材ばかりをターゲットにし、当時のビジネスフェーズに合わない採用をしていたから。結果、苦しい現状に退職者が急増し、チーム状態は悪化していきました。
苦しい状況だからこそ、視座を高く持ち踏ん張るためには「自分は何を実現したいのか」という強い思いと、チームが同じ方向に向かって泥臭く行動し続ける力が必要です。立ち上げ期こそ、ミッション・バリューに共感する人材採用を妥協せずできるかが、非常に重要でした。
立ち上げフェーズから成長期へ
失敗から学んで改善を繰り返した結果、現在の海外事業は立ち上げ期を乗り越えて成長期に入りました。最初こそ、現地の日系企業を中心に開拓をしていましたが、現在は非日系企業との契約も増え、SPEEDA全体の売り上げの10%超を海外が占めるまでに成長しています。
さらにここから成長速度を加速させていくには、組織として一枚岩となり、徹底したユーザー視点を持って各メンバーが自立して動けるようになること。
そこで今回、全てのアジア拠点からメンバーを集め、SPEEDAアジア初の試みとなるオフサイト合宿が開催されました。合宿のメインコンテツは、ユーザベースの価値観である「7つのルール(現「The 7 Values」)」についてメンバー全員が考えを深める「バリューセッション」です。

この合宿を開催し、海外拠点のメンバーにあらためてバリューを考えてもらう機会を設けた、SPEEDAアジアCEOの内藤靖統と、東南アジア営業責任者の高橋浩太郎に、合宿開催の背景にあった思いや、今SPEEDAアジアで何が起きているのかについて話を聞きました。
内藤 靖統(以下「内藤」):
最大の目的は、SPEEDAアジア事業として、チームの一体感をつくることでした。普段はアジア各地の拠点に分かれて仕事をしているので、みんなで1つのことに取り組むことを通じて、結束を強めたいと考えていました。
普段からSlackなどでやり取りはしているものの、業務以外のコミュニケーションが発生しづらかったり、組織が拡大するなかで一度も顔を合わせたことのないメンバーが増えていることに危機感をもっていました。しかもここからの急成長を実現するためには、チーム一丸となっていく必要がある。そこで今回のオフサイト合宿を企画しました。加えると、アジアチーム全員でなにか楽しいことをしたいという単純な思いもありました。
内藤:
合宿中には、どの市場を攻めるのか、SPEEDAをどのように進化させていくのかという事業戦略の共有セッションもおこないました。そこでSPEEDAアジア事業がチームとしてどこに向かうのか、目的地を示しています。
対して、バリューセッションを行ったのは、その目的地に、どういう姿勢で向かうのか、心構えや気持ちの強度を揃えたかったからです。ただ、揃えるといっても、私や他のマネジメントから枠を与えるというのではなく、アジア事業内のバリューを体現しているリーダーの話から学ぼう、というものでした。
オフサイトでの、事業戦略セッションとバリューセッションの合わせ技で、チームに一体感と躍動感をもたらすことを狙いました。

高橋 浩太郎(以下「高橋」):
具体的には、アジアチームでは今期、7つのルールから「自由主義で行こう」と「ユーザーの理想から始める」の2つを特に注力するバリューとして定めました。
セッションでは、この2つのバリューをさらに腹落ちさせるために、東京オフィスのカルチャーチームが中心となってコンテンツを組み立て、ワークショップを行いました。選出したバリューリーダーたちが12に分けたグループをまわりながら、バリューにまつわるエピソードを共有するというもの。
たとえば「ユーザーの理想から始める」なら、お客様からの声を地道に拾い続けプロダクトに反映させることで、お褒めの言葉をもらえた話。「自由主義で行こう」なら、事業をより良くする為、現場メンバーが自ら立ち上げたプロジェクトの話などです。
メンバーはリーダーたちの話に真剣に耳を傾け、自分達が感じている課題や次の具体的ステップとして何ができるか、熱いディスカッションを交わしました。

内藤:
現在、アジア事業には、日系のお客様だけではなくローカル企業のお客様も多数いらっしゃいます。あたりまえですが、国が違えばニーズも千差万別。今まで以上にユーザーのニーズを敏感に汲み取り、ユーザーの理想に立ち返ってサービスを作っていくことが非常に重要なため、「ユーザーの理想から始める」を選びました。
また、「自由主義で行こう」には、「常識にとらわれずに自由にアイディアを出して率先して実現しよう」という意味があります。事業の成長スピードをもう一段加速させるために、アジア事業のメンバーそれぞれがイニシアティブを持ち挑戦してほしいとの思いから選びました。
事業がおかれている状況によって、フォーカスするバリューを決めて意識を集結させることで、より高い結果を出すことができるはず。SPEEDAアジアにおいても、全員がリーダーになったつもりで事業に参加し、イニシアティブを取ってほしいという思いから、この2つを選びました。
バリューの浸透=時間×頻度
高橋:
バリューの浸透には、時間と頻度が必要だと思っています。そこで、7つのルールに関係する言葉を日常的に使うようにしています。
たとえば「お客様をスピードで驚かせようぜ」とか、「ユーザーファーストじゃない?」といった感じで。各メンバーが日々の業務で、何かを意思決定するシーンが多々あります。その時の判断軸として、ユーザベースの7つのルールを意識してもらえる様、自らも言葉に出すように努めています。
とはいえ、本社と海外各拠点との間で、バリュー浸透の為の活動や歴史も違いがあるため、温度感の差が出てしまっている事は否めないんですが、現状は仕方がないとも思っています。
むしろ今回の合宿をきっかけに、SPEEDAアジア内で良い意味での内輪感が出ればいいですね。SPEEDAアジアで一体感を出すことで、各メンバーが自ら発信したり、何かを企画したり、そういったアクションが増えてくることを期待しています。そのプロセスづくりについては、本社メンバーと協力しながらも、海外メンバー主導で進めて行ければ良いですね。
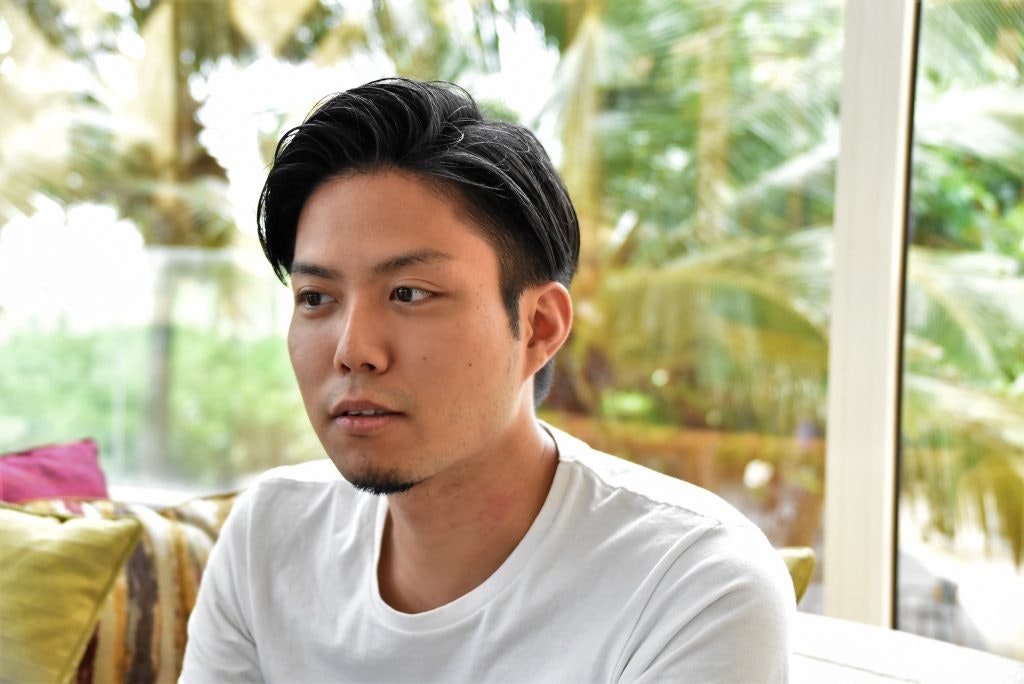
SPEEDAアジアが目指す未来
内藤:
チームとしては、この群雄割拠な状況の中で1つ抜け出た状態、「アジアの情報だったらSPEEDAだよね」と思ってもらえる状態をつくっていきたいです。そのためにも、ローカルマネジメントに変えなくてはいけないと考えています。もっと多様なマネジメント体制を作っていき、彼らのバックグラウンドも踏まえたカルチャー醸成をしていきたいですね。
高橋:
今は、各国のナショナルスタッフが少しずつ増えてきて、きちんと組織として機能するように、いろいろな手立てを打たなくてはいけないタイミングです。
まずは、国や地域は離れていても同じベクトルで走っていけるようなチームの一体感、環境を作っていかなければなりません。これは、日本のやり方も知っていて、かつローカルの肌感覚を持っている僕らの責任。
強いグローバルチームをつくり、アジアNo.1の企業・業界情報プラットフォームを実現できるよう、バリューを浸透させながら全力で走りたいと考えています。

本記事にはすでに退職したメンバーも含まれております(組織名・役職は当時)









