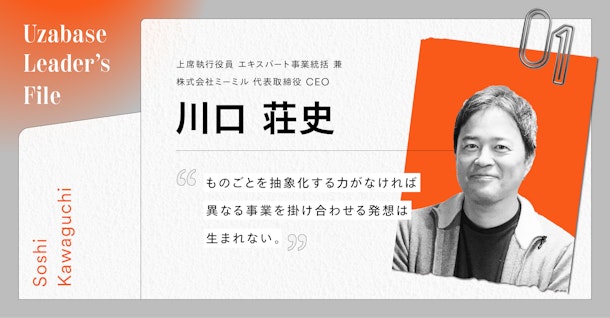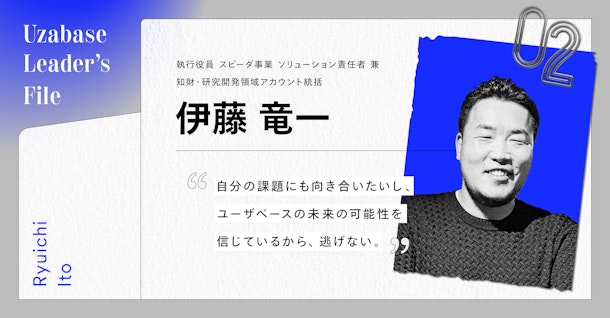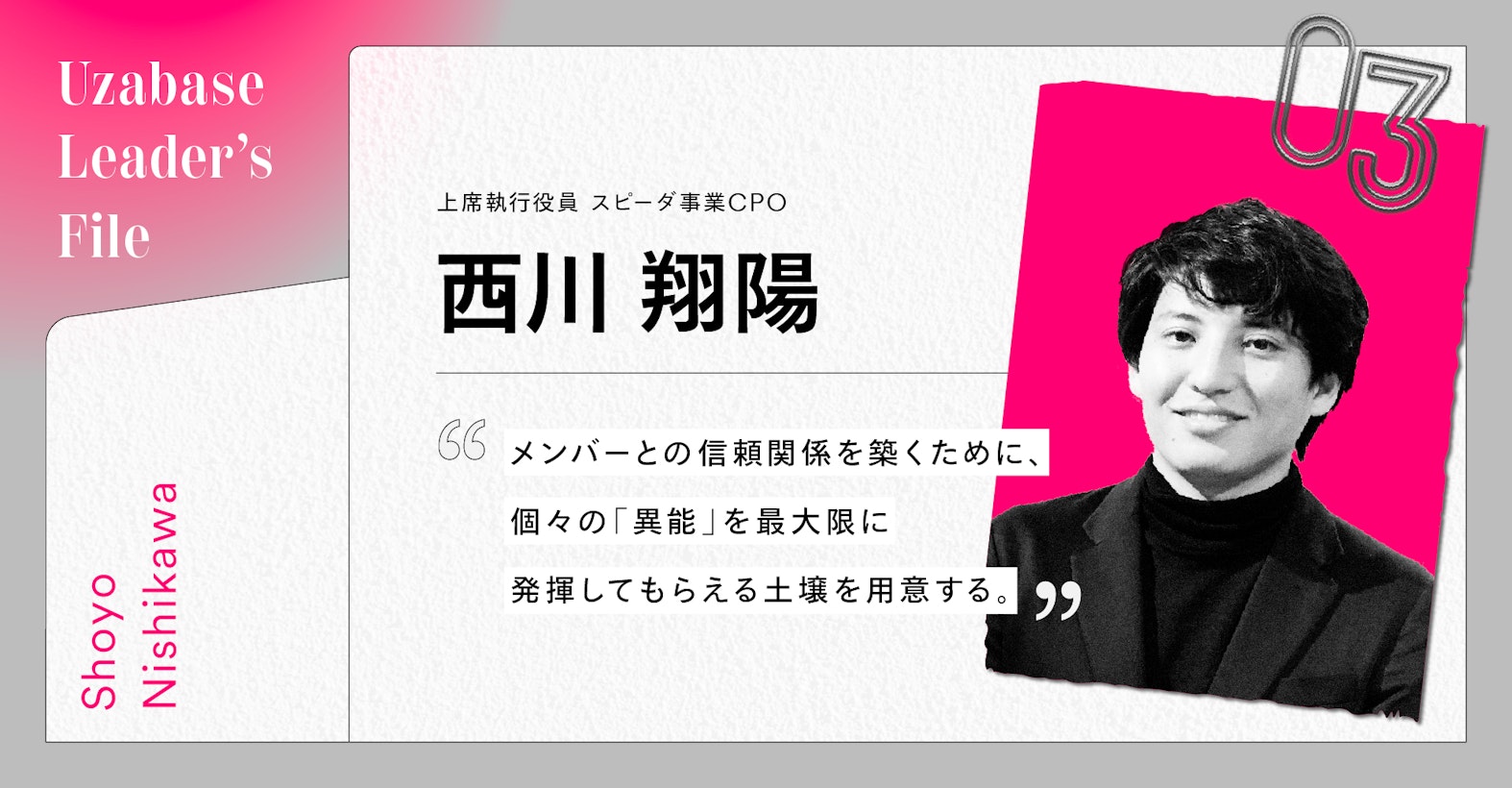「美点凝視」──個々の異能を活かして信頼関係を構築する
プロダクトが素晴らしく、細部までユーザーの利用シーンに拘っている。非常に素晴らしい経営者がいる。カルチャーに対して役割関係なく社員みんながオーナーシップを持っている。この3つの要素を見て、ユーザベースは前職以上の会社になると感じたからです。
ユーザベースに入社した当時は明確なキャリアプランは描いておらず、ただ「自分の手でグローバルカンパニーを生み出したい」という気持ちだけでしたね。グローバルカンパニーを生み出す仲間の一員になりたいと考えていました。
ただ、社長にはなりたかった(笑)。前職時代も、実はそう思っていたんです。両親も祖父も商売をする社長一家で経営の楽しさを身近に感じていて。
とはいえ、当時は自分で起業することはあまり考えていませんでした。起業そのものよりもミッションに興味があって、いかにより多くの人に深く感動していただけるかを何より優先したいと思っていたんです。
ポジションが変わるごとに、事業を多面的に見る力が身についていると感じています。ただ、僕が自ら希望して異動したことはなく、ただひたすら「事業や会社のボトルネックを解決したい」という想いを持って課題に取り組んでいたら、どんどん領域が移り変わっていった感覚ですね。実は入社してから一度もキャリアプランを描いたことがないんです。

執行役員になって、ものごとを長期思考で考えるようになりました。かつ、自分の手で解決しなくていいものは、できるだけ解決しないようにと思うようになりました。
「自分でやってしまう=余裕がない」だと考えていて。自分自身も含めチーム全体の失敗を「ここまで許容しよう」と思いながら進められるかは、大事なポイントだと思いますね。
自分のやり方や期限でものごとを進めるのは大事な要素のひとつではあるんですが、究極的にはユーザーの価値や事業が成長すること、一緒に働く仲間が楽しいと思ってくれることを達成できればいい。自分の役割としてコミットしている・約束してる結果を、組織として出せるかどうかが重要なんです。
実際、自分でやるよりもみんなでやったほうが、結果的に「早い」んですよ。ある個人で早く仕上げたことって、翌四半期もその人が同じことをしなければいけなくなる。それを30回繰り返さなければいけないんだったら、仲間が増えてできるほうが早く終わるし、想像してもいない可能性が開くことがあるんですよね。
役員になってからは、いかにその仕組みを構築するかを考えるようになりました。たとえば、ものごとがうまくいかないときって問題の解き方がわかっていないというよりは、仲間との関係性がよくないとか、十分な情報が行き届いていないことや、社内外にいるステークホルダーとよいチームをつくられていないことのほうが多い。多様な職種1つひとつに向き合う中で多面的に経営課題をみる機会に恵まれて、それを解決できる構造をつくることに取り組むようになりました。
考え方が変わった要因として、達成しなければいけない目標が高くなったことが挙げられると思います。抱える課題が複雑化してきているので、1つひとつの個別具体事象を解決しにいく取り組みをしていては間に合わない。だから個別具体事象が発生しても、チームとして解決できる構造をつくる必要があると思ったんです。
「美点凝視」をすることです。どんな人にも美しい点、良い点がある。そこをしっかり凝視するんです。「この人にはこんなすごい部分があるんだ」というリスペクトを持つと、強みに目がいくようになる。その強みを最大限に発揮してもらえる土壌をできる限り用意する。
「美点」をユーザベースのValueで言うと「異能」です。個々の異能をどう活かすかを、リーダーとして考えています。
ユーザベースは好奇心旺盛な人が多いので、そうしたコミュニケーションで悩んだことはないですね。ワクワクするビジョンを描くと、ついてきてくれる人が多い。
どちらかというと、既存の取り組みと新規の取り組みとのバランスに悩むことのほうが多いです。十分な挑戦への投資を行うために、辞めることも同時に決めていくことや、新規の取り組みに熱中しすぎて、既存のお客様に約束した価値をおろそかにしないよう、お客様の動向を注視し続けるようにしています。
挑戦と好奇心──リーダーとしての原動力
稲垣さん(稲垣 裕介/ユーザベースCEO)、佐久間(佐久間 衡/元ユーザベースCo-CEO)さんですね。2人は人生で最も影響を受けたリーダーです。
佐久間さんからは、自己変革のプロセスを学びました。自らさまざまなことを学び、自分ごと化して、自分を変容させる。彼はこれを異常なスピードでこなしているんですよね。
稲垣さんは愛情と信頼によって組織を前進させる人ですね。短期的な利益を考えると、人は邪悪な手段に出ることがあります。でも稲垣さんはステークホルダーへの愛を持って、こちらから先に信頼して、長期でよいプロダクトを提供しようとしています。
お客様に対して誠実でいるのは一番大切にしていることです。あとは、好奇心ではないかと。
「ユーザベースをグローバルカンパニーにしたい」という想いに向かって、我々が大切にしなければいけない視点は、グローバルカンパニーの経営スタイルやプロダクトのつくり方、展開の仕方を学ぶことだと考えていて。そこに対する探究や学習は、楽しんで人一倍している自負があります。それを事業に落とし込むことを期待されているのではないかと思いますね。

好奇心を持って挑戦し続けること自体を稲垣さん、佐久間さんから教わったと思っています。無理して好奇心を高めているわけではなく、「毎日発見があっておもしろい」と心から思えていますね。
たとえば仲間との1on1でも、「こんな仕事ができておもしろかった」と聞くと、1年前は達成できなかったような高い目標を仲間とともに達成できて、そこに喜びを見出してくれているんだなと思うと嬉しいし、誇らしい。
新しい機能をリリースして既存のお客様からフィードバックをいただいたときも、嬉しく思うと同時に「ユーザーのニーズに応えるためにもっと勉強しなければ」と思います。
同じようにメンバーにもワクワクしながら仕事をしてほしいと考えています。そのためには、メンバーの強みを活かせる機会を僕がどれだけ設計できるか。「こんな機会があればこの人は絶対輝ける」という機会をセッティングしたうえで、新しいチャレンジを定義しないといけないと思っています。
「失敗できない=余裕がない」失敗を許容できる組織経営を
旧SPEEDA(現スピーダ経済情報リサーチ)のレベニュー組織の責任者をしていたときに、目標未達で終わってしまったことです。無謀な目標だと認識していたにもかかわらずそれを強行して、かつ短期的な解決方法で臨んでしまい、長期的な目線でのチームづくりができませんでした。
長期目線の話はせず、その年の目標達成に向けて走り続けていたら、僕自身はもちろん、チームにも余裕や楽しみがなくなりました。本来ワクワクしながら仕事するために入社したのに、目標達成するためだけの組織みたいになってしまって……それは大きな失敗でした。当時の自分の雰囲気は相当ピリピリしていましたね。
リーダーからいちメンバーに戻って、1人ひとりのユーザーや仲間を大切にするところから再スタートしました。
あらためてユーザベースの商売の本質に向き合うことで、そもそも僕は本来、目の前のユーザーがハッピーになることが大事だと思っていたんだと再認識できたし、目の前のお客様をおろそかにするようなグロースはしたくないと考えるようになったんです。それを実現する方法は何だろう? とあらためて考えられるようになりましたね。
失敗を学びに変えられるよう、視点の変化や言語化の手伝いをしています。あとは、同じような失敗をしたことがある人との対話を促して、失敗から気づきを得てもらうようにしています。
ただ、そもそも「失敗してはいけない=余裕がない」ということなので、失敗を許容できるように組織経営することが大事なのではないかと思いますね。もちろん、大失敗はよくないので、トライのモジュールは定義して、その中で自由に挑戦してもらうようにしています。

ワクワク仕事をするために「リーダー」であることを意識しない
「リーダー」であることを意識しないことですね。その人の最大のパフォーマンスが発揮できるのは、楽しく仕事ができているときなんです。「リーダー」を意識すると変に肩肘を張ってしまう。それ以上に、ワクワクすることを考えるのが大事だなと思います。
より大きなビジョンを描くのがリーダーの責務だと思います。リーダーがビッグビジョンを描けば、メンバーは「とんでもないことを言ってるな。でもやるしかないな」と思うのではないかと願っています。
また、ビッグビジョンを描きながらも任せられる点はどんどん任せる。案外大切なのは、辞めることをはっきりすること。主体性のある仲間が多いので、主体性で悩むことはあまりないですが、いろいろやり過ぎたり、先が見えない中で時間や体力を使ってしまったり、未知のことに孤独に挑戦しすぎて苦手なことに取り組んでしまったりして、それが大きな成果に結びつかないことがあると感じてます。
長期的にお客様が喜び、事業が成長する構造が描けるか、強みを活かしきれるチーム編成が組めているかを大事にしています。この2つがあると、主体性を爆発させられると思います。どちらかというと、よりチャレンジングで成長性の高い経営活動へ焦点を絞り、大きく、長くその主体性が保てる構造にしていくことに時間を使うことが多いかなと思います。
高品質なデータを扱うユーザベースは、AI領域で価値発揮しやすい
現在取り組んでいる、生成AIを使った新規事業の開発です。
ユーザベースはAI時代における「強み」を持った会社です。これまでのAIは、LLM(Large Language Model/大規模言語処理)で大量のデータをいかに適切に処理するかが技術の中心でした。けれども、ここから先は高品質なデータが重要です。
ユーザベースはこれまで、経済領域において専門性の高いデータを取り扱ってきました。今後、AI開発で信頼性と品質が高いデータが欠かせなくなる局面においては、こうした専門性高いデータを扱う我々は価値を発揮しやすいんです。ユーザベースのアセットと生成AIは非常に相性がいいと考えています。

現在のリソース配分の多くは、スピーダ事業全体の長期的な方向性を定めていくために、ユーザベースの強みをあらためて追究することに充てています。そして、新規の領域では自らもお客様との対話やエンジニアとプロダクトをつくる現場に入っています。
先ほど話したAI領域の新たなプロダクト開発に加え、データフィード事業にも注力し始めています。AIソリューションを開発する際、それを裏で支えるために生成されたデータアセットを活用したいというお客様に、データを供給する事業を開始する予定です。
グローバルカンパニーを生み出すために、すべての国のメンバーが顧客起点思考を持つ
従来のSaaSのイメージから良い意味で転換し、NewsPicksも含めた国内最大級の経済情報アセットを元にあらゆるお客様に提供出来る会社になり、いろいろな企業の意志決定シーンにお役立ちしていること、また、グローバルでの新たな成長角度を描いていることを目指しています。組織の在り方も、これまでシンプルな構造に変化してきましたが、その甲斐があって、より新たなソリューションを加速度的に提供できる体制が整ってきました。
「グローバルカンパニーを生み出すこと」。その一点です。
ゆくゆくは「本社」の概念をなくしたいですね。日本「本社」と海外「拠点」という考え方をなくしてこそ、グローバルカンパニーだと思っています。
グローバルで働く仲間、およびグローバルのお客様に「私のための会社であり、私のためのプロダクト」と感じてもらえるような会社にしたいです。
そのためには、各地域の素晴らしい仲間が、各地域のお客様のために驚くような価値を発揮し、提供できる仕組みを整えていく必要があります。
ユーザベースが持つ顧客起点思考を、すべての国のメンバーが持ち、お客様に近いところでプロダクト開発に取り組み、提供するために、現在の組織体系をより飛躍させていかなければと考えています。

編集後記
これまでUzabase Journalに何度も登場している西川。実は私がインタビューするのは今回が初めてでした。全社会などで、生成AIに関する新規事業の話をめちゃくちゃ楽しそうに話しているのを見ているので、このタイミングでインタビューできて良かったです!
「Uzabase Leader's File」は今回で3本目ですが、それぞれの役員の特徴はもちろん、共通点も見えてきました。シリーズを通して読んでいただくと、ユーザベースのカルチャーや大切にしている価値観が見えてくるはずです。ぜひ他の記事もご覧ください!