なぜユーザベースに入社しようと思ったんですか?
前職はコロプラというゲーム会社で、マーケティングを担当していました。コーポレート側からそれぞれのゲームを組織横断的にマーケティングしていた感じです。いろいろと経験できるのは楽しかったんですが、たくさんのゲームを扱うからこそ、その1つひとつをなかなか身近に感じられていませんでした。
当時は転職を真剣に考えていた訳ではないんですけど、ユーザベースに興味をもったきっかけは、SPEEDAのマーケティングの統括をしていた相羽さん(相羽 輝/元ユーザベースメンバー・現Flyle 取締役COO)から、Wantedly経由で「広告のインハウス化をしてくれる人を探しています」というメッセージをもらったことでした。
コロプラ時代にお世話になっていた先輩の伊澤さん(伊澤 太郎/現 Contents Partnerships Teamリーダー)が、ユーザベースに入社していたことは知っていました。だから、いつもは反応していなかったメッセージにも目が止まって。それに人事からではなく、マーケティングの責任者から直接メッセージが届いたことを面白く感じたので、伊澤さんにも相談して話を聞いてみることにしました。
そこからランチを含めて6回くらいかな。マーケティング部門の皆さんに時間をもらって、丁寧にヒアリングをさせていただきました。そこで印象的だったのが「SPEEDAはこんなに素晴らしいサービスでね!」って、皆さんが熱弁していたことです。事業に対する誇りをすごく感じましたね。「こんな環境でマーケティングを担ってみたい!」って率直にユーザベースに入りたいと思いました。
SPEEDAユーザーの多くは大企業の方々ですが、私は大企業に所属したこともなかったし、入社するまでSPEEDAを触ったこともありませんでした。そもそも経済情報に関わりたい意志があったわけでもなかったので、本当に知らないことだらけでした。
「マーケティングって、自分の言葉で発信していかなきゃいけないことも多いのに、自分にできるのかな」って不安に思っていて……。でも思った以上に、ユーザーの方々にわからないことを聞いたり、いろいろなバックグラウンドを持つユーザベースメンバーたちに力を借りたりする機会があって、そうしているうちに「私にもできるかも」と思えるようになったんです。
現在の仕事内容と、仕事でワクワクしていることを教えてください。
仕事内容は、SPEEDAの成長をマーケティングから促進することです。SPEEDAにまだ興味を持っていない人たちに振り向いてもらえるような広告やコンテンツをつくったり、セミナーを企画したりしています。そこで興味を持ってもらえた人に、インサイドセールスのメンバーがそれぞれの課題に合ったSPEEDAの事例や活用方法を、個別にご案内しています。
広告やコンテンツをつくるにあたっては、どういう切り口だったら興味を持ってくれるかを考えます。そのためにはSPEEDAを使ってくださる経営企画や新規事業開発の方々が、今何に困っていて、どういう情報がほしいかを把握しないといけないですよね。でもB2Bの業界について、私が当事者の気持ちを考えるのは難しくて……。
前職のゲーム会社では、ゲームをプレイすればすぐにユーザーに会える環境でした。オフラインの集まりもありましたし、社内ユーザーも多かったんですね。でもSPEEDAのような、自分の肌感が薄いB2Bのプロダクトで、かつユーザーに会う機会がほとんどない状況では、何をつくって発信すればいいのか、確信が持てませんでした。
そこからとにかくユーザーに会いに行く機会をつくるように動いた結果、今ではユーザーの方々と一緒にセミナーを企画してモデレーターとして参加してもらったり、SPEEDAをどんな風に活用すると良いのか話してもらったりと、マーケティングメッセージを共創する関係性が徐々にできていきました。
私自身ユーザーの皆さんとの対話が「こういう課題を解決できるコンテンツをつくればいいんだ!」という確信にもつながったし、結果として自身の仕事の幅も広がりました。この頃からマーケティングが担う役割について、より広く考えるようになりました。「今SPEEDAでできること」を伝えるだけでなく、「SPEEDAユーザーは今何に困っているのか」をいち早くキャッチし社内にも伝えていくことが、サービスの進化にもつながります。
たとえば最近だとESGをテーマとしたセミナーやユーザーMeetupを開催し、その内容を事業にフィードバックしたり。ユーザーの皆さんとコンテンツを一緒に共創し、メッセージを伝播させて、事業の未来を考えていく過程にワクワクしていますね。
仕事で忘れられないエピソードはありますか?
あるSPEEDAの定例会で、メンバーにA4サイズくらいの手持ちの紙に、各々が感じている課題を書いてもらったことがありました。同じ課題感を持つ人のところに集まってもらったところ、一番人が集まったのが「ユーザーの顔が見えない」という課題だったんです。それは私自身も悩んでいたことだったし、SPEEDA組織としても解決するべきポイントだなと改めて感じました。それからユーザーとの接点を模索し始めました。
初めは宇佐美さん(宇佐美 信乃/元SPEEDA Japan 執行役員CCO)が提案してくれたSPEEDAカフェでした。ユーザーが困っていることに対して、カスタマーサクセスや開発担当の有志メンバーが1時間ほど相談に乗るカフェを開いてみたんです。
飲み物をサーブする人は、あえて普段ユーザーと関わりのない人に担当してもらいました。その時に「初めてユーザーが何に悩んでいるかを知った」というメンバーが多かったんですよ。とても意味がある場だと思いました。
運営リソースの見直しがありSPEEDAカフェは一旦終了しましたが、このような場を点ではなくコミュニティで広げることができたら、ユーザーとの自然なつながりができると感じました。
今はFacebook上に、新規事業や経営企画に携わる方とつながるコミュニティを運営しています。そこで月に2回ほど、各社が事例を持ち寄って議論しているんです。今後さまざまな部署の人たちを巻き込んでいきたいと思っていて、事業とユーザーの距離をコミュニティという場を通して近づけられたらなと思っています。
それからもう1つ、ユーザベースにオープンコミュニケーションの文化があってよかったと感じた、忘れられないエピソードがあります。チームがどんどん拡大していく中で、組織のマネジメントの見直しをしていた2021年夏ごろ、入社して2ヶ月の志賀さん(志賀 康平/現 INITIAL Marketing & Branding Team リーダー)が、チームのリーダーになりました。
私は社歴が長いしマーケティング業務の理解もあったので、メンバーだけどリーダーの志賀さんに教える機会が多かったんですね。そのことに対して、立場が逆転してしまうというか……お互いにやりづらさを感じることがありました。それを心配したJJさん(酒居 潤平/現:コーポレート執行役員CMO 兼 NewsPicks Stage. 事業責任者)が連絡をくれて、3人で何回か話をすることになったんです。
その時に、どんなコミュニケーションにストレスを感じるか、どんな仕事に対して気分が乗らないかなど、お互いが感じている意見や不安をめちゃくちゃオープンに話しました。対話する中で、役割分担さえ上手くいけばすごく良い補完関係を築けるということに気がついたので、結果的にリーダーを2人でやろうということになりました。
そもそも「2人でリーダーをやる選択肢があるんだ」と、話してみてスッキリした部分は大きかったですし、自分が働きやすい環境は対話によって自分でつくることができるんだって思いましたね。
The 7 Valuesの中で、一番好きなバリューは何ですか?
「異能は才能」ですね。「ユーザーの理想から始める」という言葉も好きだったけど、リーダーになってみて「異能は才能」っていいなと改めて思います。私にないスキルや強みを持っている人がチームに集まっているので、みんなで力を合わせたら何ができるだろう? と考えるようになりました。
さらには自分のチームメンバーだけではなくて、チームに足りない能力があればチーム外の人たちの力も借りれば良いことにも最近気づきました。たとえば今ユーザーコミュニティを一緒に運営しているカスタマーサクセスのメンバーや、セミナー集客を支えてくれている業務委託のプロフェッショナルの人、もちろんユーザーの皆さんもそうです。そういう人たちと一緒に、それぞれのスキルを組み合わせて何ができるかを考えるのは楽しいです。
こうしてチームをつくっていく中で、「私自身の異能って何だろう?」と考える機会も増えました。それぞれが自分の異能を自覚してさらに磨いていくことが、「異能は才能」の体現につながるんじゃないかなと思っています。
たとえば周りのみんなには、私の強みは企画力だと言われます。自分はクリエイティビティのある人間だとは思っていなかったので、意外でした。でも企画力って、相手に共感して、伝えたいメッセージ・コンテンツを考えることでもありますよね。人の話を聞いて想像していく過程で「こんなコンテンツがいいのでは」と思いつく──そういうものが企画力だと考えると、確かに自分の強みの1つなのかなって思っています。
異能は意外と自覚できていないこともあって、このバリューを支えているのはユーザベースのフィードバックし合う文化かもしれませんね。
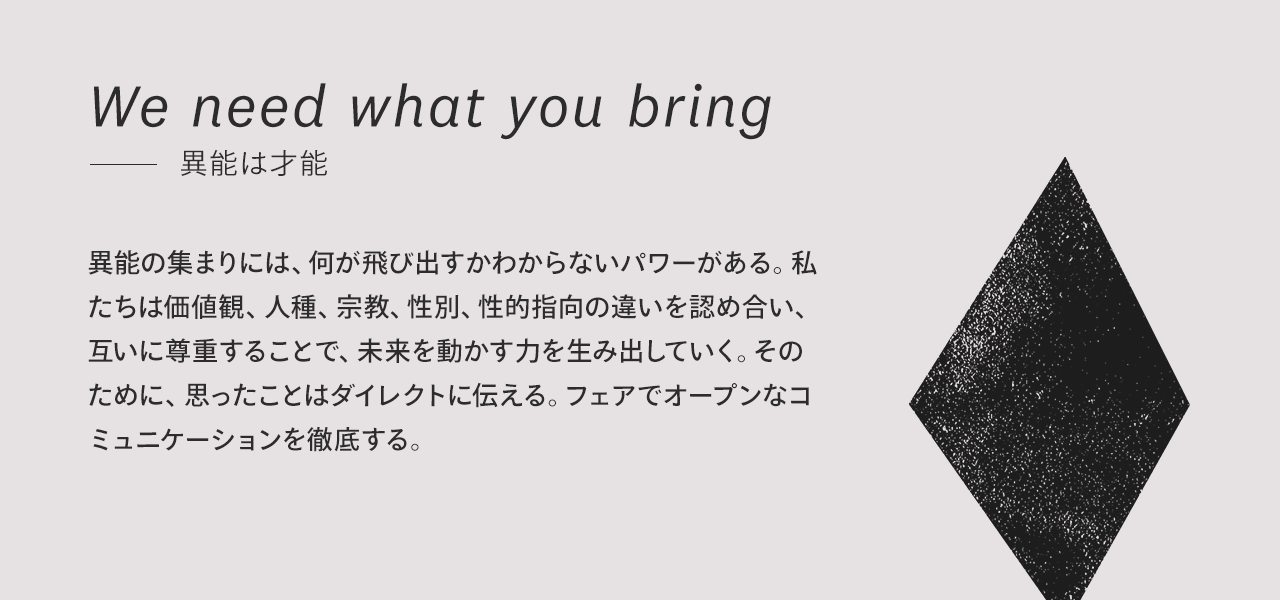
今後挑戦したいことは?
まずはユーザーコミュニティを立ち上げきることが目標です。コミュニティがゴールというよりは、顧客起点で事業を進化させていける場所をつくりたいです。カスタマーサクセスやマーケだけでなく、アナリストや、サービス開発をしているメンバーなど、事業全体の人たちをもっと巻き込んでいきたいですね。
そのためには、ユーザーが集まりたくなる場所をつくる必要があるからその設計をしようと思います。ユーザーの皆さんにとっても、企業変革というゴールに最短でたどりつくために「このコミュニティに参加しておこう」と思っていただけるものをつくりたいと思っています。
足下ではまだリーダーとして試行錯誤中なので、引き続き悩みながらも、いいチームをつくれたらなって思っています。「こうならないといけない」とか、「この人に追いつかないと」とかではなく、それぞれが自分の役割や成長領域を認識して働ける環境がいいと感じます。
究極のところ、みんな楽しく働きたいですよね(笑)。私が思う「楽しい」というのはたぶん「成長実感があるかどうか」なんですね。たとえば私は、入社当初にオンライン広告を担当している段階では、セミナーなどのコンテンツを企画できるようになるとは思っていませんでした。でも慣れない仕事に挑戦しながら成長し、そして実績をつくってきたからこそ、今SPEEDAのマーケティング戦略の幅を広げることができたんだと思います。
こんな感じで、それぞれの挑戦とスキルアップが、事業成長につながるような設計をしていくことがリーダーの役目だと思っていますし、私の目指すところです。
本記事に登場するメンバーはすでに退職しております(組織名・役職は当時)








