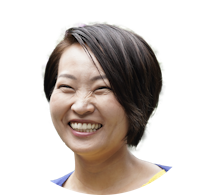1. はじめてリーダーを打診されたとき、どう思った?
監査法人時代は、基本的に入社年次に応じてリーダーになるので、打診されたときも、正直「そんなもんかな」くらいの印象しかありませんでした。はじめてリーダーになったのは、入社3年目のときでした。
はじめて任されたプロジェクトが終わり、チームをまとめる能力を評価されたときは、「え、こんなんでいいの? それなら早く言ってよ!」っていう感じでした(笑)。
監査法人では若くしてインチャージ(主任)になるし、人の入れ替わりも激しいので、自分のチームをつくるためには、まず1年生を育てあげていく必要があるんです。これが結構大変でした。しかも、せっかく育てたと思ったら、いわゆる力の強いマネージャーにあっさり引き抜かれたりもするので、結局インチャージになりたての頃は、常に新しいメンバーの育成に追われていた記憶があります。
公認会計士として専門性をもって分析・問題発見・調書化する能力とリーダーシップとは、全くの別物なんだなと実感しました。
でも、数年後に彼らが立派に他社で活躍していたり、駐在員としてアサインされたりとキャリアを積んでいる報告を受けるのは嬉しかったですよ。本当にいい後輩たちでした。
2. ユーザベースで実際にリーダーをやってみてどう?
監査法人で会計士として働く専門性と、事業会社で監査役や内部監査として働く専門性は異なるので、単純な比較は難しいなと思います。
ユーザベースには、最初は常勤監査役としてジョインして、今は内部監査の部門にいます。非常勤の監査等委員取締役のサポートも続けています。
基本的に会計士のみで構成される監査法人とは異なり、事業会社にはいろいろなバックグラウンドの人がいますよね。ユーザベースに入社して、良い悪いという意味ではなく、その人やキャリアによって思考回路や前提となる成果物イメージが大きく異なるということを学んだ気がします。
たとえば、1つの事象に対して「コレが漏れていました」で終わる人と、「コレが漏れているということは、こっちもこの見方であらためてチェックした方がいいかも」と考えられる人の差は、結構大きいと思います。
ユーザベースは事業会社だから、監査や法律の知識がない各事業部のメンバーとやり取りすることも多いです。その際、書類を見てジャッジメントして終わりではなく、ある程度ローコンテクストにすることを意識し、言葉を尽くして丁寧に説明することが大切です。
でも、その重要性をメンバーに伝えるのはなかなか難しい。そういう大変さはありますね。
3. 何を大事にしているの? 仕事だけでなく、人生でも。
自分が心身ともにヘルシー&ハッピーでいることですね。身体が弱ると心も弱るので、睡眠とビタミン剤は特に大事にしています。
精神面については、考えや基準が相手と異なるようなとき、そもそも他人の考えや他人からの評価を、真に受ける必要性があるのかどうかを考えた上で、異なる意見を受け取るようにしています。受け止めなくてもいいことを真に受けて必要以上に傷つく必要はないし、受け止めるべきことは自分の意志で「自分にとって良いことだ」と意思決定した上で受け止める話なので、いずれにせよハッピーでいられます。
仕事上では、いくら心の中で腹が立っていても、アウトプットだけは柔らかくするように気をつけています。たとえば、何か問題が起きたとき、まず「注意する or しない」で分岐するんです。言葉にして相手に伝えるか、それとも伝えないか、その意思決定の分岐です。
決定要因は、相手に言って伝わる人か、言葉を尽くしても歩み寄れない人かどうか。歩み寄れない人に指摘しても、「この人、ユーザベースのバリューに合わないな」と思われて終わるだけなんで、言いません。「なるほど、言ってくれてありがとうございます」という捉え方をしてくれる人には、ちゃんと言いたいなと思っています。
子どもに対しては、できるだけ温かいスタンスでいることを心がけています。子どもはそういうのに敏感なので。とは言え、ついつい自分に負けて強く叱っちゃうこともありますけどね。床に牛乳をこぼされたときとか(笑)。
4. ワークライフバランスについて、どう考え、実践している?
子育てについてはファミリーサポートや親族、行政などの手をたくさん借りて、なんとか回している状態です。でもそれは悪いことじゃなくて。私自身も幼い頃は近所の人に預けられている時間が長かったので、家族だけでなく「地域で育てる」という観点は大事ですし、色んな視点が入ることは、教育上もいいことだと思っています。
私の母は元教職員で、私がまだ生後3ヶ月のときに育休から復職して、65歳の定年を過ぎてからも70歳まで市役所の職員として働いていました。母いわく「早く復帰しないと家計を助けられなかったし、キャリアが閉ざされる危機感があった」のだそうです。
自分のことを後回しにしてでも、自分や家族だけでなく世の中のために尽くすという母の姿勢は、私にとって一番のロールモデルになっていると思います。私を含め今の世代は、男女雇用機会均等法のない「平等でなかった時代」を、なんとか乗り越えてきた人たちの恩恵を受けているんですよね。
以前、厚生労働省で男女雇用機会均等法の制定に関わった岩田喜美枝さんから直接お話を聞く機会がありました。岩田さんは、自らも仕事と育児を両立しながら、女性が当たり前のように働ける法律をつくった方です。そういう制度面を整えてくれた方はもちろん、1人ひとりの「働く女性たち」が、今の時代をつくってくれたんだと思うんです。
男女共同参画局の資料で、女性の年齢別労働人口を表したグラフがあるんですが、M字カーブの凹みがだんだん浅くなってきているんですよね。そういうのを見ると、言い方は古いかもしれませんが、「女性の社会進出」の歴史的な軌跡の中にいるんだなぁ、と実感します。
けれど今の20代、30代の女性にとっては、「育児も働くことも両方がんばって!」という社会的期待を重荷だと感じる人もいるかもしれません。そんな思いもあって、「仕事も子どもも自分の人生も諦めたくない」というワーキングペアレンツと想いをともにする場として、「Career Juggling」という活動を立ち上げました。
最近はなかなか活動できていないんですけど、子育て中のメンバーをゲストに迎えたPodcastも配信しているんですよ。これからはもう少し頑張っていきたいなと思っています。ユーザベースメンバーのみなさんはどなたでもウェルカムですので、ぜひ参加してほしいですね!
5. うまくいかなかったとき、どうした?
私自身、中学・高校・大学とプロテスタント系の学校で、中高時代は毎朝礼拝もあったので、キリスト教的な考え方が性格に合っているような気がするんですよね。そういうこともあって、「神様、今くださっている私への試練は、一体何が目的なのですか? そのうち意味がわかるんですか? ……でもぶっちゃけ、私はもう限界です」と神様に質問するようにしています。
もちろん、すぐに答えが出ないこともありますが、「自分の使命は神様の意図があって存在する」という価値観なので、答えを待つというか、耐えしのぎます。
耐えしのぐときは、その困りごとの延長線上にあるポジティブな場面をイメージします。辛いことを実際に引き寄せるのは、辛いイメージをぐるぐる思考させることから始まる、と聞いたことがあるので、頭の中はあえてお花畑にしているんです(笑)。
この思考法にたどり着いたのは、ジニーちゃん(Jinny Cheong/Assurance & Consulting Division Division Leader)から勧められた『人生を導く5つの目的』(リック・ウォレン著)という本を読んだことがきっかけでした。
学生時代の教えの1つに「地の塩 世の光」というものがありました。これは「塩気がない世は意味がない。光があってもそれが机の下では意味がない。あなたの才能を、世に役立たせなさい」というような意味なんです。当時はあまりピンとこなかったんですが、社会人になってからは、深く理解できるようになりました。たぶん私には、「自分のことだけ考える」というのが合わないんだなと思います。
6. メンバーと話すときに意識していること
価値観のところでお話ししたスタンスは意識していますね。あと、開発部門には「ペアプログラミング」という手法があると思うんですけど、私のチームでも結構2人1組で仕事することが多いんですね。形が決まっていないものをつくるケースは、特に話しながら作業をすると、意図がちゃんと伝わっていい成果物ができて効率的だし、雑談もはさみながら楽しくやれるのでおすすめです。
こういう作業を一緒にやると、相手の仕事のクセや大事にしたいポイントがわかってくるんですよね。一緒に作業することで、相手が大事にしている「非言語的な価値観」が伝わるのでしょうね。プライベートのことを話すこともあって、ちょっと家族みたいになっていく気がします。
他には、相手の良い部分や、私がその人にどんな役割を期待しているのかなどを端的に伝えること。それから今は表面化していないけれど、今後障壁となりそうなことを聞くことも大切にしていますね。
7. 1on1のときに気をつけていることは?
以前は定期的な1on1はしていなかったんですが、1on1研修を受けてから、月1回のペースでやり始めました。研修では未来志向で接するようにと強調されたので、「これができるようになったら、どういう景色が広がるのか」とか「そのためには何から手を付けたらいいのか」とか、普段自分では言語化しないこと、頭の中でモヤッとしていることの整理をするようにしています。
8. メンバーと意見が対立したとき、どうしているか?
自分がこだわりたいポイントをちゃんと話すことは大事にしています。それでも正解がなくて相手の意見に一理あるな、と思うときは相手を信じ、任せて様子をみます。そもそもマインド的にシニアなメンバーが多いので、チーム内で対立することはあまりないですね。
9. ユーザベースのD&Iについてどう思う? 嶋田さんにとってのD&Iは?
最近、長女が発達障害(ADHD・ASD)だということが分かり、それを契機にいろいろと勉強したんです。その中で、障がいというのは「医学モデル」「社会モデル」「人権モデル」に分かれるということを知ったんですね。「医学モデル」で障がいを判断しているお医者さんに「社会モデル」や「人権モデル」といった対応策の話をしても通じないのは当たり前だと納得しました。
ユーザベースの場合、The 7 Valuesの1つである「自由主義でいこう」などに表れる、個人のwillを尊重する組織風土は、概念的に「人権モデル」に近く、とても素晴らしいと思っています。
今後は、ただ掲げるだけではなく、もう1歩踏み込んで「この人の特性を生かすためには、どんな役割・責任範囲が適切か」といった、より具体的な施策が求められるのかなと。
あとはラベリングやアンコンシャスバイアスを取り払う「文化形成」も大切だと感じています。
10. D&Iに取り組むメリットは?
多様な人が安心して働きやすくすることで、組織が強くなり、事業成長につながるというメリットがあるんじゃないでしょうか。
ただ、ユーザベースはNPO法人ではなく営利会社なので、もっと利益に直結するようなD&I施策が求められるのかなぁ。極端に言えば投資家を通じて高齢者の年金などにも貢献できるわけですもんね。
とはいえ、たとえば障がい者雇用というテーマの場合、実際に雇用したとしてもそこで働く人たちが幸せじゃないのだとしたら、それはちょっと違うかなとは思います。
もちろん、それは雇用を控えろという意味ではありません。コミュニケーション方法などの環境面までしっかり整えて、ちゃんとその人がそこで活躍できてバリューを発揮できる状態で雇用しないと、本人も周りもハッピーじゃないと思います。その人の状況に合わせて、周りが環境調整できないのに雇用するのはどうかなぁ、と感じることはあります。
<私にとってのD&I>
NPO法人はびりすのホームページです。このNPO法人は児童発達支援事業や、放課後デイサービス事業などを行っていて、子どもの発達に真摯に向き合っています。このNPO法人が掲げる「すべての人にはGiftがある。」というコンセプトに強く共感します。
誰しも、自分らしさを大切にしながら、自分の好きなことに自分の好きなやり方で没頭する権利があるという、このNPO法人の考え方はまさに私の描くD&Iの理想的なあり方です。