NewsPicksに入る前は全然違う仕事をしていました。入社数年前から個人でインフォグラフィックをつくっていたんですよ。もし仕事に活かすならメディア業界だろうと思っていたけど、特に何かアクションを起こしていたわけでもなくて。どこかから声がかかるわけでも当然なくて、趣味で続けようと思っていました。
そんなとき、僕が書いた本を読んだ佐々木紀彦さん(NewsPicks 初代編集長)から連絡があって。個人サイトのメールフォームから問い合わせてくれたんです。それが2014年の夏頃、NewsPicksの編集部を立ち上げる直前のことでした。
佐々木さんの著書を読んでいたので「あの本の人だ!」と驚きました。NewsPicksのオリジナルコンテンツに、インフォグラフィックを入れたいと言ってくれて「あ、コレは僕がずっと望んでいたインフォグラフィックの使われ方だ」と思ったんです。
最初は佐々木さんとカフェで会って、その後すぐに稲垣さん・梅田さん(稲垣 裕介・梅田 優祐/いずれも共同創業者)との面接が決まりました。会って話してみて、ビジョンにすごく共感できたんですよ。それで迷わず飛び込みました。正式な入社は2014年12月ですが、9月からコンテンツ制作を手伝い始めたので、編集部立ち上げ時のコンテンツには、最初からインフォグラフィックが入っています。
入ってみて「やりたいこと」と「場」が完全に一致した! って感覚でした。
最初はひたすら記事コンテンツをつくっていました。今は編集者とデザイナーがタッグを組んで記事をつくることがほとんどですが、当時は僕自身もリサーチして記事をかいたり、バナーをつくったり。編集者が増えるまでの2〜3年は、記事を書きながらユーザベースの名刺デザインの相談も受けていたし、IRのスライドデザインもやっていて、とにかくカオスでしたね(笑)。
直近2年はソーシャル編集部を立ち上げていました。でも「編集部」と名乗りつつ、組織図的には1人の部署なんです。それまではクリエイティブ部門のマネジメントをしていましたが、今はマーケティングやクリエイティブなど他の部門のメンバーに協力してもらいつつ、バーチャル組織みたいな形でやっています。
仕事内容は、簡単に言うとSNS用のコンテンツ企画・制作と流通を考えること。コンテンツの流通網を整えるのが面白いなと思っています。NewsPicksには良いコンテンツがたくさんあるけど、まだまだ知られていないんですよ。
講師を務めているNewsPicks NewSchoolやアカデミアの生徒さんと話していても、見られていない、知られていなくて……まだ「街の中にある1つの店」でしかない。それを外に出す──SNSという「外の街」に流通させることでNewsPicksのコンテンツに触れる体験を増やすのが仕事です。僕は「試し読み体験を増やす」って言っています。
もう1つの仕事としては、2020年10月にアプリのUIリニューアルをしたタイミングで、ショートコンテンツというスワイプ型の画像コンテンツを導入しました。そのフォーマットを企画しました。
「外の街」であるSNSからNewsPicksに来てもらっても、無料ユーザーの方々ってNewsPicksの有料コンテンツに触れる機会が少ないなと思っていて。ショートコンテンツによって、SNSでやっている「試し読み体験」をつくる発想ですね。NewsPicksのコンテンツへの入口と体験の階段をつくりたいと考えています。
映画の予告編みたいに、有料コンテンツって「ある程度知っている」という安心感を得た上で買うのが一般的になってきているんじゃないかなと思うんです。初期ユーザーは思い切って買ってくれていたけど、今のNewsPicksのフェーズでは予告編のように「ある程度知っている」状態をつくるのが大事かなと。
もともと何かを生み出すのが好きで、例えばインフォグラフィックのスマホフォーマットを生み出して「こんなの見たことない!」って言われたのはワクワクしました。そこで一旦「型」ができたのでチームに引き継いで、ソーシャル編集部の立ち上げ時に画像を4枚組で使うフォーマットをつくって──どんどん新しい「型」をつくるのが好きなんだと思います。
最初はインフォグラフィックって海の物とも山の物ともつかぬものだと思われていたけど、ユーザーの良い反応が増えてきて、編集者が一緒にやりたいと言ってくれたり、ブランドストーリー(広告コンテンツ)に使いたいと言われたりするようになったんですよ。手を動かし、形として見せることで、そこから広がっていくのは面白いし、社会を動かすうえで大事な要素なんだろうなって思っています。
僕の中でユーザベースやNewsPicksのイメージは「公園」なんですよ。会社という公園があって、いろんなグループや人がいろんなことをやっていて。子どもの頃って、面白そうな遊びをやっているところに人が集まってきたじゃないですか。その感じが理想の仕事の状態だなと思っているんです。
今やっているショートコンテンツもある程度結果が出てきて、編集者から「一緒にやりたい」って相談が来たり、自発的に他チームのメンバーがコンテンツ制作に参加してくれるフェーズに入っています。つまり「公園で人が集まってくる状態」になっているわけです。そういう状態がすごく良いし、面白いんです。
フォーマットをつくって、ある程度「型化」した時点で僕の手を離れるのは淋しいけど、そういう新たなフォーマットを生み出すライフサイクルを何回も体験できるのは、NewsPicksの良いところですね。
ただフォーマットを変えてもなかなかうまくいかなくて、新たなデバイスの登場など一定期間で起きる大きな変化のタイミングに乗れると、うまくいくのかなと思っています。そういう大きな変化は数年毎に絶対に起きるし、その変化の波に乗っかっていかないと、逆にサービスは廃れていってしまうんじゃないかなって。
フォーマットは変わっていくし、サービス自体の器が何年もずっと同じなのはおそらくダメ。そう考えると、何年かに一度くるタイミングに関われるのは嬉しいしワクワクしますね。
恵比寿から六本木にオフィスを移転した2018年くらいに、会社のフェーズが0→1から10→100のフェーズに変わりました。その頃から、佐々木さんや梅田さんが出席する会議に出ることが増えたんです。
入社当初は、編集部の立ち上げやアカデミア事業、NewsPicks Studiosの立ち上げなど、佐々木さんと一緒に仕事をする機会が多かったんですよ。そのときに佐々木さんが描く「コンテンツ文脈でのビッグピクチャー」みたいなものにはついていけたし、ある程度理解もできていたんですね。
でも梅田さんは全然別の軸で大きな絵を描いていて。僕がついていけないくらいの大きな構想を持っている梅田さんと、コンテンツ文脈で同じく大きな絵を描く佐々木さん。2人のスケールについていこうと思って、ちょっと自分のバランスを崩してしまったんです。
会議の数も増えて、手を動かしたいのに浅くしか関われない案件が増えてしまい、自分の中のアイデンティティが揺らいでしまったんですね。今の状況でのベストは何か、自分らしさとは何か──その結果、広く浅く「何でも屋」みたいに顔を出すのは違うんじゃないかと考えて、やることを絞ろうと決めました。
自分を見失いそうな状況だったので、自分が戦う場所はどこなのか、戻る場所はどこなのかを確かめたくて、マネジメントから離れ、ゲリラ的に動ける状態に戻ったんです。入社当初のような個の状態に戻ってみて、「あ、戦えるな」と分かって、自信を回復できました。このときに立ち上げたのが、今のソーシャル編集部です。
何でバランスを崩しかけたのか振り返ってみると、2017〜2018年頃に稲垣さんが「コンフォートゾーンを超えよう」みたいな話をよくしていたんですよ。その影響を受けたのがキッカケだったかなと思います。
自分がコンフォートゾーンを超えるためには、それまでやっていたコンテンツ制作や、編集部での仕事以上のことをやってみなければならないんだと考えたんです。それで自分のやることを広げることにチャレンジしてみたけど、僕はそういうコンフォートゾーンの突破の仕方は向いていないと気づいたんですね。
短距離走者が長距離走を走れるようになるとか、野球選手がサッカー選手になるような広げ方ではなく、例えばサッカーでフォワードの選手がミッドフィルダーもできるようになるとか、競技が決まっているほうがいい。そう気づけたことで、短距離走という競技の中でスピードを上げるようなことが僕なりの「コンフォートゾーンを超える」ことなんだって解釈に変わったんです。
その気づきを得る前はしんどかったですね。短距離走も長距離走もできる――現場の仕事もできて、マネジメントもできるようになることが、コンフォートゾーンを超える・広げることだと思ってしまっていましたから。それができる人もいるけれど、僕はそういうタイプではないと今では分かっています。
だから「絞る」ことを非常に大事にしているんです。もちろん将来的に広がる仕事をやらないわけではないけれど、ソーシャル編集部を少人数でやってみて、「この戦い方はできる」って状態になってきました。今後もゲリラ戦で転戦していくのか、当時うまくいかなかった「広げること」を、今の自分なりのやり方で再チャレンジしてみるのか、どちらの道に進むか、今まさに考えている段階です。
「創造性がなければ意味がない」かな。
なぜかというと、本当は「The 7 Values」って1つ足りていないと思っているんですよ。それは何かというと、「迷ったら挑戦」と近いんだけど、「迷ったときに目先の利益ではなく、大義を取る」みたいなもの。安易な道を選ぶのではなく、大きな絵の方を取るようなものがほしいなって。そのニュアンスに近いのが「創造性がなければ意味がない」かなと思っています。
以前はすごく個人主義だったんですよ。自由と責任がセットなのは重々承知していたけど、「でも自由でいたいじゃん」みたいな(笑)。でも自分だけ良ければいい、自分の業種だけうまくいっていればいいわけじゃないんですよね。その先があって、この現状を享受できている裏には何があるんだろう? って考えるようになったんです。
今の環境は放っておいても出来上がった幸せではなく、誰かが創造的なアプローチを駆使してつくってくれているものだと思うんですね。だから今、仕事があるのはすごく恵まれているんだ、そんな風に考えるようになって、より「創造性」の意義を感じるようになりました。
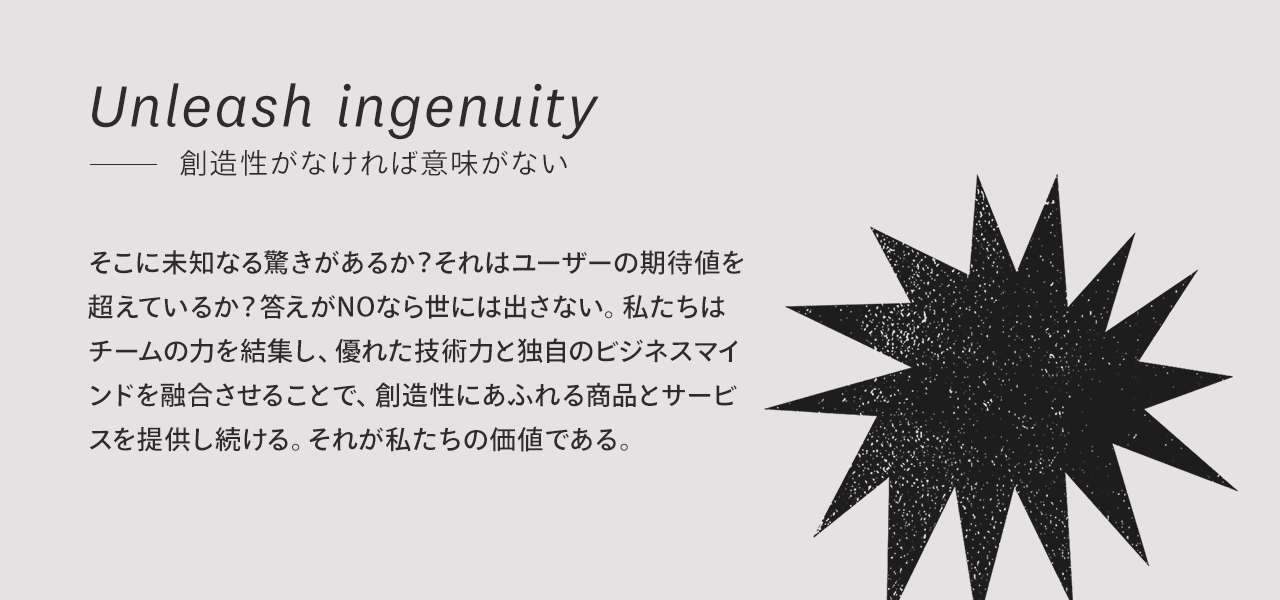
個人軸でいうと、おそらく僕はどんな形であれ、一生インフォグラフィックや情報デザイン――情報の課題をグラフィックで解決することをやっていくんだと思っています。だから最近は「インフォメーション・デザイナー」と名乗ることにしています。
それを会社軸で考えると、NewsPicksとしてグラフィックを使って情報を活用したいとなったとき、そこで何か関われたらいいなと考えています。そうすることで、社会課題の解決に何かしらつながるようなことができたらなって。
今、一番注目している社会課題は「気候変動」。それについて考えると眠れなくなるくらい。今のような生活を続けたい。たとえばMacやiPhoneを使い続けたいけど、気候変動に関する本をたくさん読んでみたら、今のまま放っておいて何もしなければ、今の生活や環境を維持できないことが分かってきて……。
いろいろなビジネス課題もあるけど、全てのベースには環境があるじゃないですか。今の環境があるから、仕事も平和な生活もあるわけです。だから環境に対して自分は何ができるのか──できることはちっぽけかもしれないけど、意識していたいと思います。
以前は新しいテクノロジーやサービスに関心があったけど、最近はほとんど情報を追っていないんですよ。だって土台となる社会や環境があってこそのテクノロジーじゃないですか。理想主義者っぽいことを言っているけど(笑)、大もとのインプットが足りなかったのかなと思っていて。
今は自分のアップデートに時間をかけている感じです。NewsPicksに入った当時は、「テック万歳!」「メディアやコンテンツの力で課題解決していくぞ!」って信じていたし、それで実際に数年間やってきました。
でも社会が変わっていくにつれて、自分自身のOSが古くなってきた気がしたんですよ。OSが古くなっているのに、ソフト──ちょっとしたサービスの知識などを新しくしてもダメなんですね。僕自身のOSをメジャーアップデートする必要があるなと感じていて。だからOSの上に乗るソフトやアプリ、サービスへの関心が一旦薄れている感覚です。いずれまた興味を持ち始めるのかもしれませんけど。
もう1つの関心事としては、気候変動・環境問題によって資本主義をどう変えていくのか、どんな形にアップデートするのがいいのか、めちゃくちゃ気になっています。NewsPicksを含むユーザベースグループが「経済情報で、世界を変える」とミッションに掲げている以上、その変化に参加していなければならないと思うし、そのリードカンパニー、資本主義をアップデートする中心にいる企業にならないといけないんじゃないかなと考えているんです。
直近2年くらいかけて、ようやく自分のOSをアップデートできてきたので、その資本主義の変化に新しい自分で関わっていきたい。自分自身でも大きく変わった感覚があるので、どんな風に関わっていけるか、今からワクワクしています。








