なぜユーザベースに転職しようと思ったんですか?
経歴をお話しすると、まず大学卒業後、新卒でワークスアプリケーションズに入りました。
入社を決めた最も大きな理由は、最初から大きな裁量権を持って仕事がしたいと強く考えていたから。私が就活していた当時は、人気企業は下積みがすごく長いとか、管理職になるまで10年かかるみたいな話を聞いたことがあって。
成長カーブが一番急な20代を下積みに使うのは、すごくもったいないなと思ったんです。 ぴよぴよ🐤 くてもいいから、難しい仕事を任せてもらえる環境を探しており、ワークスならそれができそうだと考え、入社を決めました。
ワークスでは、退職するまでの6年半ずっと会計システムの事業部で、顧客課題を自社製品で解決するカスタマーサクセスと、品質保証の仕事を約3年ずつ経験しました。
仕事は充実していましたが、2010年に始めた趣味のジャズピアノ演奏が面白くなってしまい、ボストンにある某音楽学校への留学を死ぬまでに叶えたい、と思うように。そこで思い切って2013年の夏にワークスを退職し、半年間セブ島で英語の勉強をして行ってきました。
一時は本業にしようか迷うくらいピアノ演奏が好きでしたが、悩んだ末に留学を終えるタイミングでビジネスの世界に戻ることを決めました。その留学の最終月にたまたまスカウトメールをいただいたのが、ユーザベースと出会ったきっかけです。
ビジネスの世界に戻ったら、次は自分の手でプロダクトやコンテンツを企画したり、改善できるフィールドに身を置きたいと考えていました。CSポジションでの応募でしたが、財務会計やB2Bソフトウェア業界の経験が生かせそうだったこと、ユーザーの課題解決のお手伝いを通じてSPEEDA自体の改善にも関われると思い、転職を決めました。
現在の仕事内容と、仕事でワクワクしていることを教えてください。
今はB2B SaaS内のSaaS Dataチームに所属しています。仕事は大きく分けて2つあります。
1つはSPEEDA、FORCAS、INITIALに入っているデータを「つくる」仕事。「つくる」というのは、WEB上に公開されている情報を取得するオペレーションを構築し、パートナー会社さんと協力して、決められた期限までに予算内でプロダクト内に格納し続ける業務です。扱っているデータには企業の基本情報や決算説明会資料等があり、更新があると通知が来る仕組みを構築しています。
もう1つが「守る」仕事です。自社で取得したデータはもちろん、サプライヤーさんから購入したデータも含め、異常値の有無をチェックする仕組みを作っています。購入したデータもわざわざチェックする理由は、ユーザーからすればそこで問題が起こればそれは「SPEEDA・FORCAS・INITIALの体験」だから。
私たちにとってデータは、人間の血液のようなものだと思っています。綺麗なものが常に供給されないとプロダクトが死んでしまう。だから自社で取得したもの、購入したもの、その両方の品質が守備範囲である、という意識を強く持っているんです。
ワクワクするのは、新しいデータの開発をしているとき。新しいデータがプロダクトに入ることで新しいユーザーに価値を届けられるのはもちろん、アナリストやデータサイエンティストがそのデータを活用して、付加価値を生み出せる点にも可能性を感じます。
仕事で忘れられないエピソードはありますか?
いろいろありますが、最初に入ったCSチームでリーダーをやっていたときのことですね。その当時、役員からリーダーを任せて頂いたのにチームをうまくまとめられなくて……。今思えば、当時はメンバーに対するリスペクトが足りなかったんです。「自分が正しいことを言うのが大事だ」という意識が強すぎたんですね。
その意識はその後プロダクトチームに異動しても残っていて、合宿でちょっと周りの人をディスカレッジするような発言をしてしまったんですよ。それを受けて、当時のマネジャーからいただいたフィードバックを、今でもすごく覚えていて。
「合宿のときの発言で、『崎田くん』と『その他のメンバー』みたいな壁ができてしまったよね。崎田くんの言うことも分かるけど、他のみんなの意見もリスペクトされるべきだ」と言われて、すごくハッとしたんです。周囲の人を見る目がガラッと変わった瞬間でした。
そのフィードバックだけでなく、そのマネジャーが普段チームメンバーに接するときの態度からも学べることがたくさんあって。リーダーが必ずしも正しいことを言わなくてもいい、全員で良いものをつくればいいんだという考え方に変われたんです。
その後、データチームで再びリーダーを任される機会をいただいたとき、このときの学びがすごく活きました。自分がリーダーとして引っ張るときは引っ張るけど、必ずみんなの意見を引き出してからまとめるようになりましたね。
The 7 Valuesの中で、一番好きなバリューは何ですか?
やっぱり「ユーザーの理想から始める」ですね。
よくあることだと思うのが、データチームも含め、仕事って意識していないと、ただの「作業」になっちゃうんですよ。
例えば「このデータ間違っています」って指摘を受けたとき、作業としてはそれを直せば終わりなのかもしれません。でも、そういう問い合わせが来たのは、それを見つけたユーザーがいるから。その方が抱いた感情は、決して良いものではないですよね。それを想像できるかどうか、1つひとつの仕事に対して、ユーザー視点での想像力が持てるかが、とても大事だと思っているんです。
想像さえできれば、「今回はこういう問い合わせをもらったけど、他のデータは大丈夫だろうか?」って意識が向くし、再発防止に向けてメンバー間で建設的な議論が起こります。だから自分は、ユーザー視点に立つ想像力を一番大切にしています。
そしてこれは入社した後に、ユーザベースを改めて好きになったところでもあるんですが、全員が「ユーザーの理想から始める」をすごく意識して、日々の仕事や会話をしているなと感じられるんです。そんな環境で仕事できていることが、すごく嬉しいし好きなんですよ。ユーザーが主語になっている限り、組織は壊れないと思います。私たちを束ねてくれるバリューの1つですね。
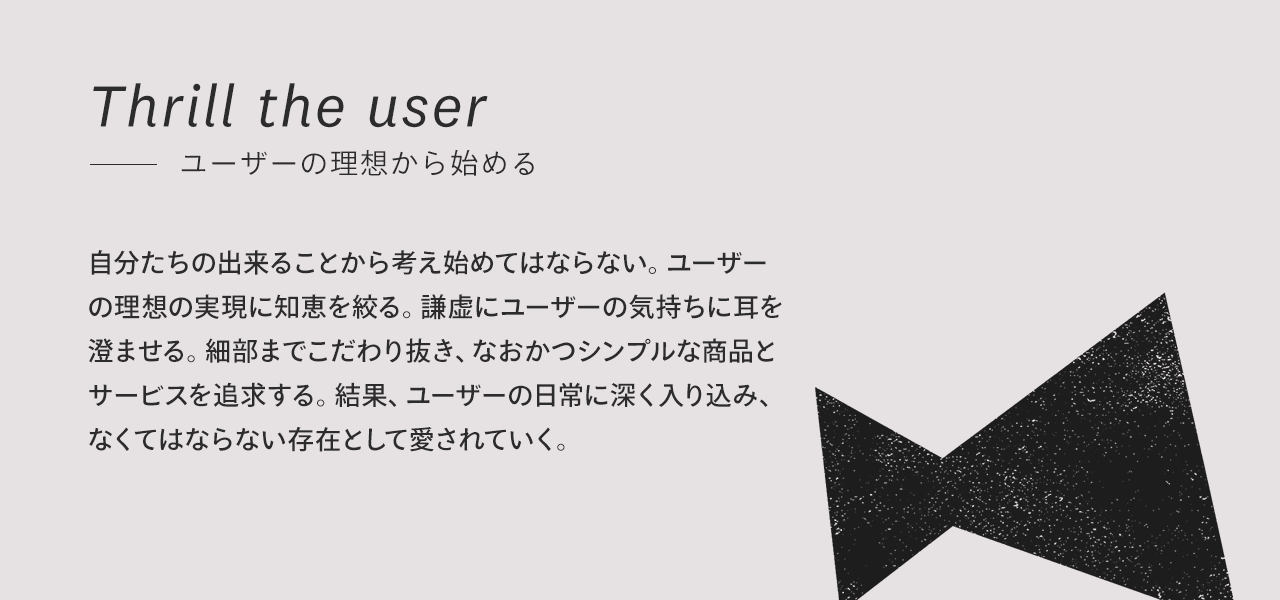
今後挑戦したいことは?
今、2つ抱えているテーマがあります。
1つは「リサーチから企画する」こと。直近でデザインリサーチを経験する機会をいただいたんですが、ユーザーのインタビューや行動から示唆を出し、そこから企画する──これをデータチームでも実践していきたいんです。データチームのようにユーザーから少し距離のあるチームでも、ちゃんとユーザーを見て企画を立て、ボトムアップでデータや機能の開発を提案していきたいと考えています。
もう1つは完全に個人的な野望なんですが(笑)、データの持っているポテンシャルをもっと開花させたいですね。今はたくさんのデータをスムーズに供給することができるようになりました。もちろん、それはとても価値のあることです。
一方、データってそのまま渡されても、何を意味するのか分からないことも多いと思うんですよ。それをユーザーが分かりやすい形で届けられるようにするとか、もっと示唆を与えるようなコンテンツに昇華できたらいいなと思っています。
テーマとして個人的に興味があるのは「データジャーナリズム」と「データビジュアライゼーション」ですね。品質の良いデータを滞りなく供給できるようになったら、そのデータを使って「こういうコンテンツをつくってみよう」「こういう見せ方をしてみよう」っていうところまでやりたいんです。もちろんユーザーにとって価値があることが前提で。データ×デザインというテーマで、付加価値を生み出していけたら嬉しいです。








