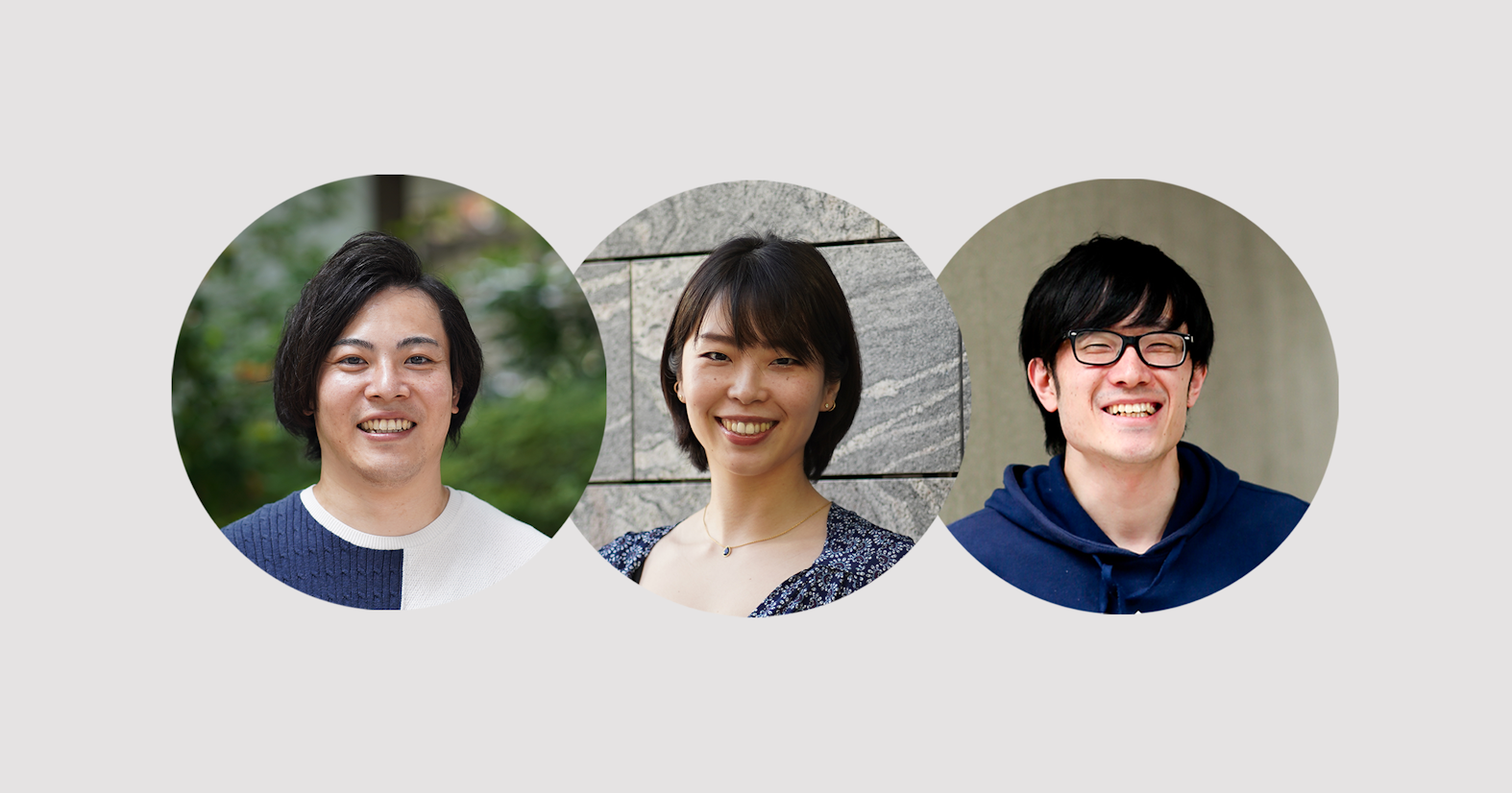外部からでは入り込めない”距離感”を解消するため事業会社へ
高橋 岳(以下「:高橋」)
僕は新卒からずっと監査法人で働いてきました。ただ、新人の頃から一度は事業会社で働きたいと漠然と思っていたんです。仕事は楽しかったんですが、入社8年目くらいでマネージャーになって、そろそろ事業会社に行きたいなと考え始めました。
監査法人をはじめファームで働く人たちは、やはり外部からクライアントである事業会社と付き合う立場なので、社内の実態がどうなっているのか深く見えないんです。さまざまなクライアントがいますが、もしかしたら実は表面的な部分しか見えていないのでは? という感覚があって、より深く入り込みたいと思っていました。
ファームの人間はクライアントの意思決定に寄り添う、応援する立場なので、自分で事業に対して何かを決めることはほとんどありません。自分でも意思決定をしてみたい思いも漠然とありました。
武田 彩香(以下「武田」):
私は逆に、あまり事業会社に行きたいとは思っていませんでした。私も新卒から弁護士事務所に所属していますが、担当していた訴訟などの仕事が楽しかったんですよ。訴訟案件は事業会社でやるより、ファームで代理人としてやるほうが楽しいと感じていて。
5〜6年は全く転職する気もなく、ずっと事務所でやっていくつもりだったんですが、留学や出向で外に出てみて、「世の中にはいろんな働き方があるんだ」と気づきました。出向先から戻ってきたのが30歳を過ぎた頃です。あと30年くらい働くことを考えたとき、本当に今の専門分野だけでやっていくのか改めて自分に問い直してみて、もっといろいろなことに挑戦したいと思ったんですね。
高橋さんが言う「外部からだと深く見えない」点をストレスに感じることも、転職を考えた理由の一つです。クライアントから依頼を受ける際も、本当はその過程で何が起きていたのか、なぜやりたいのか、もっと内側からちゃんと見て、そのうえで自分の専門知識を活かせるような仕事がしたい――そう考えて、事業会社への転職を決めました。
松栄 健介(以下「松栄」):
20代半ばでユーザベースに入り、当時は高橋さんが監査法人にいて、僕は監査を受けていた側だったんですよね。キャリアを重ねていく中で、他社の会計処理を見ておかないと自分のスキルの幅が広がらないと思い、一度ユーザベースを出ることにしたんです。
転職したのは監査法人でした。監査法人と事業会社との違いは、やはりクライアントとの距離感だと思います。監査法人にいるとき、いくらクライアントに寄り添い、パートナーとして仕事をしていても、求められるのはクライアントからもらった最小限の情報で最大限の結果を出すこと。
意思決定に資する部分の資料はもらいますが、それ以外に自分がもっとこの会社のことを知りたいと思っても、追加の資料がほしいと依頼するのは難しい。それは監査法人の仕事としてやっていることではないですから。その距離感は、当初思っていたより大きかったですね。
2年くらい監査法人にいましたが、やはり事業会社で自分事として、自社のビジネスを愛している状態で仕事をしたいと強く思い、ユーザベースに戻ってきました。今はUzabase USAとNewsPicksを主に担当しており、経営企画や事業部と毎日のように電話しながら、自分が意思決定する立場で仕事ができているので、本当に戻ってきて良かったなと思っています。

外部のプロに任せるのではなく、ディスカッションする
高橋:
僕はファームに在籍していた頃はベンチャー企業の監査をやることが多かったので、クライアントと併走してプロジェクトを遂行することが多く、距離感はあまり感じたことがなかったんです。一方、クライアントが大企業かつ縦割り型組織で、ドライな関係性だと、距離が遠いと感じることもあると思います。ユーザベースはコトに向かって、最速で最適な解を導くような文化が浸透しているので、もちろん距離感は近いですが、それよりもコミュニケーションが「速い」と感じています。
武田:
それは確かにあるかもしれません。プロファームでももちろん親身になってやりますが、あくまでクライアントはお客様です。お客様にとっては「外部の弁護士」みたいな関係にどうしてもなります。訴訟など依頼内容によっては、あくまで第三者としてやることが逆に大事な場合もありますし。だから事務所自体は自分事というより、外部のプロという姿勢でやってきたわけですが、事業会社に入ってみて「自社の一員としてやる」感覚は全然違うなと思います。
松栄:
ちょうど今、アメリカの投資案件での会計処理について、現地のコンサルタントとやり取りをしています。US-GAAP(米国会計基準)に沿う必要があり、社内の専門知識だけでは足りないので、外部の意見をいろいろ聞いているんです。我々が米国会計基準を調べ、「こういう理解をしているが、このやり方で良いか」と尋ね、先方から回答をもとにやり取りを重ねています。
社内の知識だけで足りないと思ったら、外部のコンサルを使うことは今後もあり得ます。ただ、丸投げにするのではなく、自分たちの専門知識を活かしながら、一緒に解を見つけていくような依頼の仕方をしています。
武田:
リーガルも同じです。たとえばM&Aをやる際、金融商品取引法など特定分野でプロの意見を聞かなければ分からない部分は、外部の弁護士に聞きます。返ってきた回答をそのまま社内にシェアするのではなく、あくまで自分で一度考える、調べるようにしています。聞くというより、外部の弁護士と議論する形で入ってもらうことが多いですね。
武田:
とにかく毎日忙しいです(笑)。プロファームでの忙しさに疲れて事業会社への転職を考える人も一定数いると思いますが、ユーザベースも結構忙しい。でもすごく充実しています。とにかく毎日何かしら新しいことがあるんですよ。日々新しさに順応していくことが求められるので、飽き性の人には向いているのかもしれません(笑)。
松栄:
以前は会社の規模が今ほど大きくなかったので、だいたいの情報は把握できていたんですが、今は待っていても情報が来ない点が大きく違います。ビジネス自体はすごいスピードで走るので、後からキャッチアップして、それに会計処理を合わせにいこうとしても、制約が増えていくんですよ。会計処理をこうしたいけど、後から言っても必要な資料がないから、その会計処理はできなくなってしまうわけです。
監査法人なら課題が出るたびに相談してもらえるので問題ないんですが、今のユーザベースの成長スピードだと間に合いません。Slackを見て「これは自分から聞きに行かないと取り返しがつかなくなる」みたいなことも多いので、プロファームから来た人が一番ギャップを感じるところかもしれません。
武田:
法的にどういうスキームでやろうか? から考えるのではなく、「この期間でこういう成果や経済的メリットを出したい」みたいな「あるべき」が先にあります。それをどう実現するかをリーガルや各チームのプロが知恵を絞って考えていくので、そこは大きな違いだと思います。
あとはスピード感。物事がすごいスピードで進んでいくので、通常なら倍くらい時間をかけてやるプロセスも、各チームが集まって話して、あっという間に決まって動くんですよ。ミーミルの買収時も、会社として早く実行したいというのが先にあって、一方で法的にいろいろな基準を満たす必要があったんですが、驚くほど短期間で実行しました。

多様なプロフェッショナルと共に、仕事の幅を拡げていく
松栄:
ユーザベース自体が究極のプロフェッショナルファームなのではと思っています。監査法人には会計のプロが、弁護士事務所には法律のプロがいますが、ユーザベースには各々の分野のプロが集まっているので、プロファーム出身の人は馴染みやすいと思いますよ。
武田:
そうですね。私も入社してみて、思っていた以上に違和感がありませんでした。松栄さんの言う通り、各分野のプロと仕事するようになった感覚というか。法務部としての意見を出すため、法務部長の承認をもらう、みたいなことは全然なくて、自分で考え、自分がどう思うのかを求められるケースが圧倒的に多い。それはファームにいた頃と全然変わらないですね。
高橋:
2人が言うことに同意です。多様なプロフェッショナルがいて、それぞれが意思をダイレクトに伝えられるし、そのうえでチームとして最適な解を出していこうと部門横断的に動ける。変な社内政治的なことも皆無だし、やることもシンプルなので、プロフェッショナルファーム出身者は働きやすいのかなと思います。
監査法人にも会計士だけでなく弁護士や税理士、コンサルタントもいますが、全く別の分野の方とコラボレーションする機会があまりなかったんですよ。でもユーザベースはそれぞれの分野のプロとのコラボレーションがすごく多い。リーガルや経営企画だけでなく、事業部側とのやり取りも多くて、いろいろな体験ができる面白い環境だと思います。
武田:
仕事に関しては基本的にオープンでドライ。みんなコトに向かっているので、激しいディスカッションをすることも多いんです。そのコミュニケーションをストレスに感じる人は苦しいかも知れません。
松栄:
みんなコトに向かってストレートに発言するんですよね。別に怒っているわけじゃないんだけど(笑)、それに「うっ」となっちゃう人もいると思うんですよね。最短で最適な結果を出すためにどうするか? を考えているだけなので、「社長から**って言われちゃった」みたいな、立場を気にしちゃうようなタイプは向いていないかもしれません。実際すごくフラットですし。
松栄:
何か新しい案件が発生したとき、経理・法務・営業から1人ずつ呼んで、それぞれの専門家としての意見を聞かせてもらうようなミーティングがよくあります。新しいサービスが始まるときや、新しい取引が発生するたびに、そういうミーティングが開かれて、経理としてではなく「松栄さん的に違和感ありますか?」「どういう会計処理をしたらいいですか?」と意見を聞いてもらえるのが、自分としては一番いい働き方だと思っています。
武田:
私はもともと紛争や労働法に関する案件しかほぼやっていなくて、新しいことがやりたくて転職を決めたんですが、専門だった分野に関連するポジションの紹介はたくさんあったんですよ。でも、それだとプロファームから敢えて移る意味があまり無いなと思って。
プロファームで5〜6年以上やっていると、自分が持っている専門性をそのまま戦力として活かせる転職じゃないと難しいと思いがちですが、ユーザベースは全然違うことに挑戦できるんです。実際入社半年で、TBSとの業務資本提携やミーミルの買収という、これまで全く経験のない分野の大きな案件を、メイン担当としてやらせてもらいました。willさえあればやれる環境が用意されているのは、ユーザベースで働く利点だと思います。すごくワクワクしますし、プロとして応えたいと思えます。

高橋:
僕は自分の仕事に対して説明責任を持ち、やり切り、成果にコミットすることをプロ意識と呼ぶと考えています。プロフェッショナルファームには、成果にコミットするけど、自由な人が多いと思っていて。ユーザベースも自由主義で、その裏側で成果に対してちゃんと責任を持っています。立場は違うけど、プロ意識の面で両者の根幹は似ていると思うんですね。ユーザベースは資格にこだわらず多様なプロフェッショナリズムで構成されているので、彼らと仕事をする中で自分の引き出し、幅がどんどん広がっていく感覚があります。
プロフェッショナルファームはいろいろなクライアントを相手にするので、さまざまな会社を見れるメリットがあります。一方、事業会社は1つの会社にずっと勤めることになるので、1つのことしかできないというような先入観があるような気がしていて。でもユーザベースは本当にいろいろなことができるんですよ。さまざまなグループ会社があるし、さらにどんどん広げようとしている。多様性がさらに拡がっていくようなイメージなんです。
1つの会社に勤めることに対して抱いている心配は、全くしなくていいと思います。武田さんの言う通り、willがあればどんどん任せてもらえる環境なので、ぜひ一度話を聞きにきてください!
本記事はオンライン(zoom)にて取材しました
本記事に登場するメンバーの中には、すでに退職・退任しているメンバーも含まれます(役職・所属組織名は当時)