ポニーキャニオンが抱える経営課題
松井 亮介(以下「松井」):
よろしくお願いいたします。このインタビューでは、カスタマーサクセスチームが日頃ご一緒させていただいているSPEEDAのお客様の「リアル」なイメージを、読者の皆さまにお伝えできればと思います。
まずお2人がどんな役割をされているのか、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
林 亮太郎氏(以下「林」):
よろしくお願いします。
私は昨年の8月に、ポニーキャニオンに転職してきました。前職からずっとエンターテイメント業界に関わっていて、今は「プロジェクト推進部」での新規事業開発やコンテンツ・マーケティング事業、「エリアアライアンス部」での地方自治体向けの事業などを担当しています。
檀原 由樹氏(以下「檀原」):
私は新卒でポニーキャニオンに入社しまして、現在は経営企画と人事を兼務しています。
松井:
檀原さんとは、SPEEDAご導入時のイントロダクション以来ですね。林さんは弊社のイベントにご参加いただいたり、実は自宅がご近所だったりで、日頃からとてもお世話になっているんですよね(笑)。
さっそく本題に入りたいと思いますが、ポニーキャニオンさんが現在抱えられている経営課題とは何なのでしょうか?
檀原:
私見も入りますが、大きく2つあります。1つは、当社が事業の主軸としているコンテンツを中心とした既存領域における課題です。スマホやネットの普及によってデジタルトランスフォーメーションが進んでいる中で、これまで収益の大きな部分を占めていたCDやDVDといったパッケージビジネスの市場は縮小傾向にあります。
一方でサブスクリプションサービスの台頭によって、グローバルで見ると音楽業界全体の売上は過去10年で最高になってきています。コンテンツ自体へのニーズは高まっているといえる背景のなかで、いかにデジタル化に対応したナレッジやノウハウを社内に蓄積していけるか、またそれに最適化された組織体制に転換していけるかというのが課題としてあります。
もう1つは、既存領域以外の新しいビジネスをつくっていくことです。当社のコアを軸にそこから派生した新規の事業領域をつくっていかなければなりません。
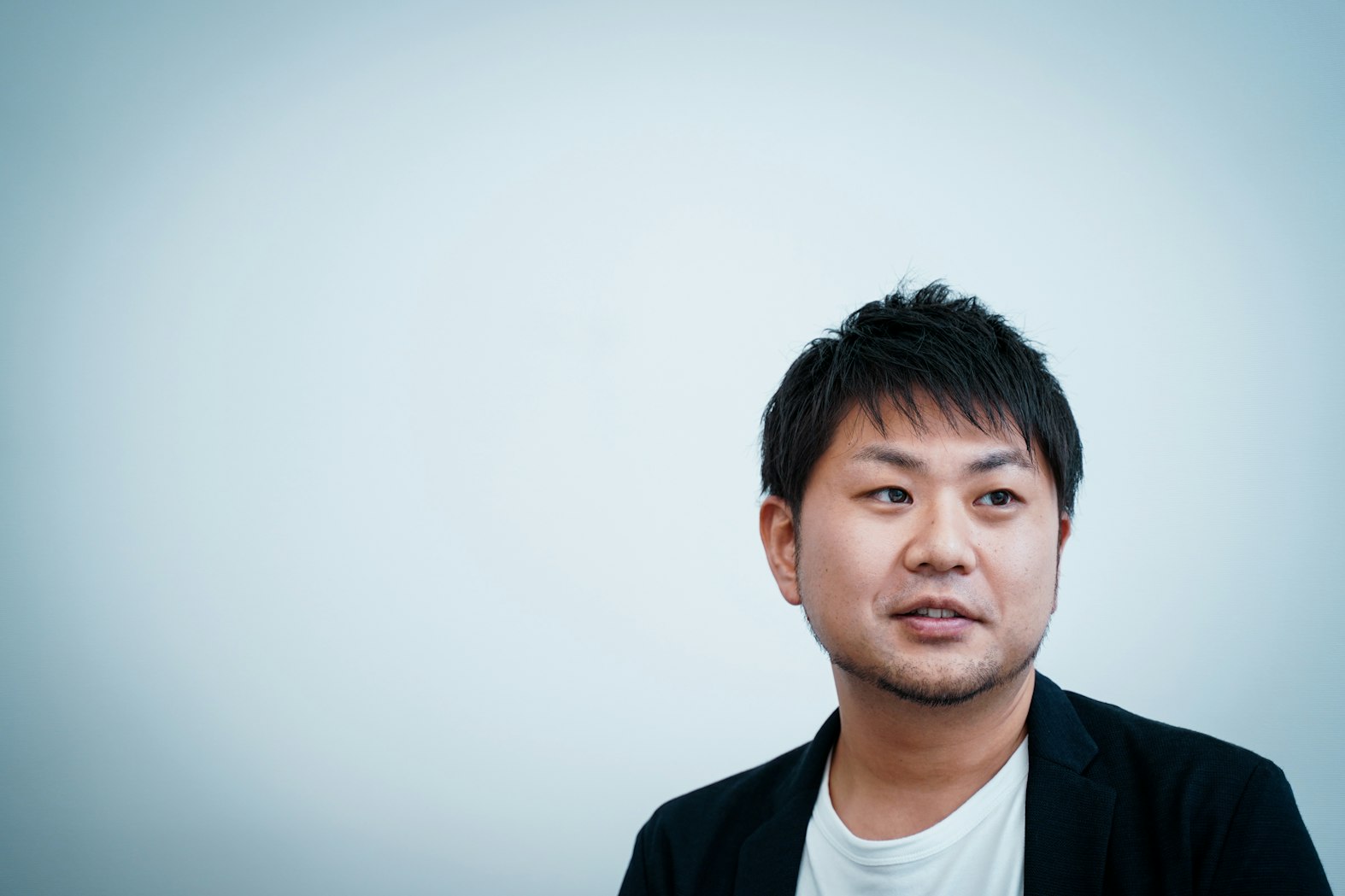
林:
すでに形となっている事業の一つとして、エリアアライアンス事業があります。これは地方自治体をお客様として、私たちのコンテンツやイベントをプロデュースするノウハウを使って、地域の活性化に向けたソリューションをご提供しています。
檀原:
また11月には、池袋に「harevutai(ハレブタイ)」という最新のテクノロジーを使った未来型のライブ劇場もオープンします。3Dホログラムスクリーンをはじめ、3つのハイスペックスクリーンを完備していて、VTuberのライブやe-sportsなどの公演も可能です。4K対応のライブ配信機材も常設して、全世界にリアルタイム配信が可能な施設となっています。
「コンテンツをつくる」がコア領域
松井:
御社内では、自社のコア領域をどのように定義されているのでしょうか?
林:
それはやはり「コンテンツをつくる」だったり、「コンテンツをつくるための人を集めることができる」といった部分でしょうか。コンテンツへのニーズが高まっている中で、弊社には、120%のクオリティでお応えできるノウハウがあるという自負があります。
檀原:
加えて、パッケージだけでなくいろいろなデジタルプラットフォームへの配信も含めて、コンテンツを生み出し、お客様へ届け、その収益をコンテンツホルダーへきちんと分配していくという、コンテンツの入口から出口までをワンストップで対応できるのが弊社の強みですね。
林:
とはいえ会社の売上としては、パッケージビジネスが占める割合もまだまだ大きいです。一方で中長期的な視点では、CDやDVDが今までのように売れ続けていくとは、やはり考えにくい。自分たちのコアが何であるかをしっかりと定義して、これまで培ってきたスキルやリソースを転用していく必要があります。

檀原:
弊社の社長(吉村隆・代表取締役社長)もよく、「90度ビジネス」という言葉を使っています。今やっているビジネスの真逆を行くのではなくて、林が言っていたようなコアな部分を軸にして、事業領域や顧客領域を広げていこうという考え方です。
音楽産業って2014年にいったん底を打って、今、世界的にはまた伸びてきています。それを牽引しているのが、音楽のサブスクリプション(定額課金)サービス。やっぱりコンテンツの力って強くて、レコードであろうがCDであろうがYouTubeであろうが、何で聴こうが人の心を動かせる価値って変わらないと思うんですよね。そこに大きな可能性があると信じています。
なのでレコード会社と言うとまだまだCDやDVDを思い浮かべる方も多いかと思いますが、そうではなく「コンテンツ」に重きを置いて事業展開をしていきたいというのが、個人的な想いです。
「未来のポニーキャニオンをつくる」ことがミッション
松井:
ありがとうございます。お二人が向き合われている経営課題の難しさがひしひしと伝わってきました。
では、そういった課題を検討するにあたって、SPEEDAが貢献できている部分はどのあたりにあるのでしょうか?
檀原:
情報収集の部分は、非常に助かっています。たとえば経営会議である企業とのアライアンスの話が出てきたときに、「その企業の株主構成は?」「直近の収支構造は?」となってもSPEEDAを使えば一発で出てくるので、だいぶスピードアップできている感覚があります。
また特定のトレンドについて書かれたレポートも参考にしています。たとえば先ほどお話しした「harevutai」で言うと、リアルライブをメインにするのか、それともVRをメインにするのかといった葛藤がありました。その際にもSPEEDAにあるVRのレポートを参考に、VRの実用化フェーズに関する自分の仮説をすぐに検証でき、そこからリアルでもVRでもなく、「ライブ配信」という新たな解も導き出せました。Googleでは探しづらい、体系化された情報に簡単にアクセスできるのは助かります。

ポニーキャニオンが2019年11月に池袋にオープンする未来型ライブ劇場 “harevutai”
松井:
何か檀原さんの中に仮説があって、それを補強したり検証したりするデータを集めるためにお役立ていただいたんですね。確かにそういう使い方をされているお客様もとても多いです。
檀原さんには、私たちが先日開催した新規事業についてのセミナーにもご参加いただきました。さまざまな企業で新規事業をご担当されているSPEEDAユーザーの方に参加いただいたのですが、檀原さんと同じように経営視点で物事を捉えられている方や、業界構造を俯瞰して見ることで企業を変えたいという志を持った方々とお話させていただくのは、私たちもとても刺激になります。
林:
僕が入社する前はSPEEDAも導入されておらず、檀原はデータ集めや資料づくりに本当に忙殺されていたんです。今ではその時間を短縮して、分析や企画などといったより本質的なことに使うことができている実感があります。
たとえば私が担当している「エリアアライアンス事業」は、私たちのコア領域であるコンテンツプロデュース、制作、ディレクションといったスキルを地方に提供することで、事業としても着実に伸びてきています。「harevutai」も、11月のオープンからが本当の勝負になります。
私たち経営戦略本部のミッションは、こういう新規事業をいくつも生み出し、未来のポニーキャニオンをつくっていくこと。より本質的なことに時間を使い、この挑戦を加速していきたいですね。
松井:
今日はインタビューにお応えいただき、本当にありがとうございました。御社が向き合われている経営課題についてのイメージがより一層深まりました。
私たちが日頃ご一緒させていただくお客様は、お2人のような「転換点」に直面している業界・企業の方が多く、正にお話いただいたような経営課題に向き合っておられます。
私がこの仕事をしていてエキサイティングに感じるのは、御社のようなエンターテインメント業界から、製造業やメディア、通信、小売まで多種多様な産業に関わる方と、業界の潮流や企業課題をディスカッションできるパートナーでもあることです。SPEEDAというプロダクトを通してだけでなく、時にはSPEEDAに留まらない多面的な話題にも向き合える存在でありたいと思っています。
皆さまが向き合われている大きなミッションと比べると、今の私たちがお役に立てているのは、限定的な範囲だと思います。それでも意義ある一翼を担えるよう、プロダクトの進化も見据えながら、引き続きご一緒させていただけると嬉しいです。今日は本当にありがとうございました!











